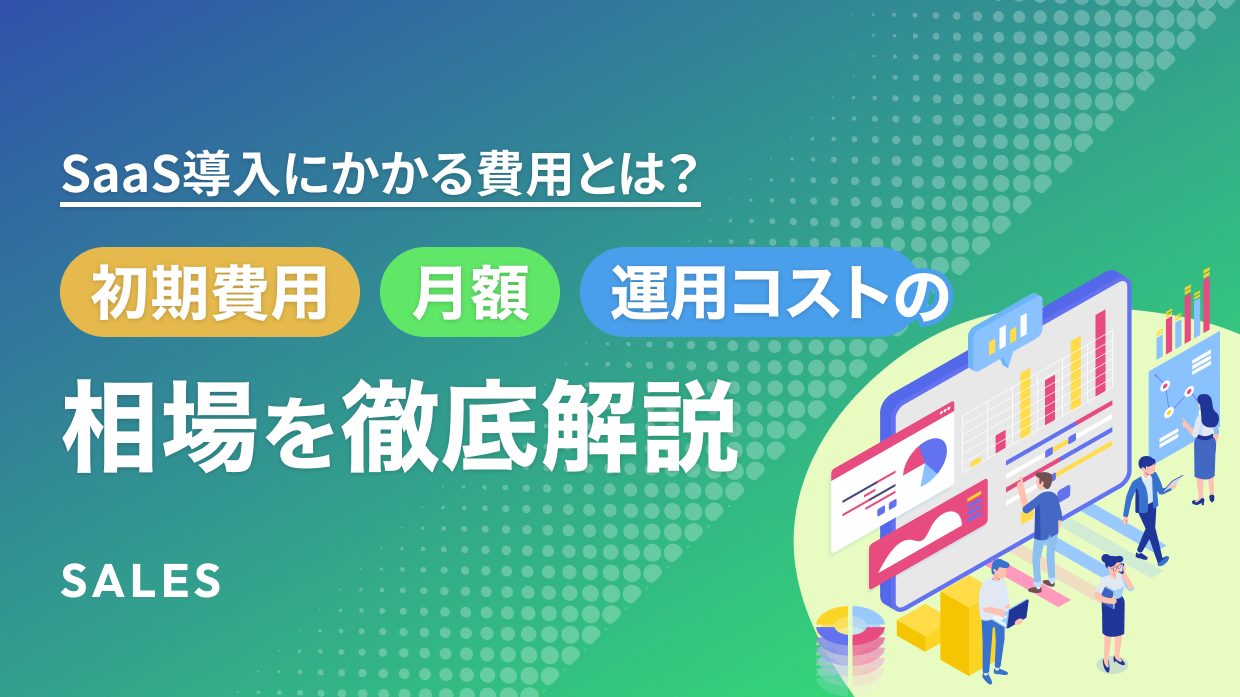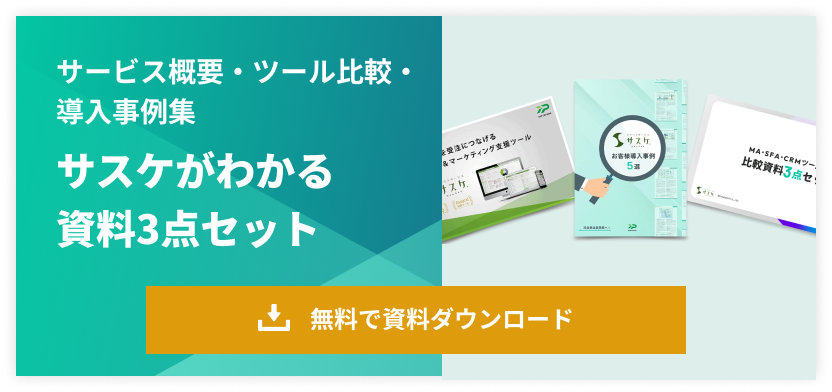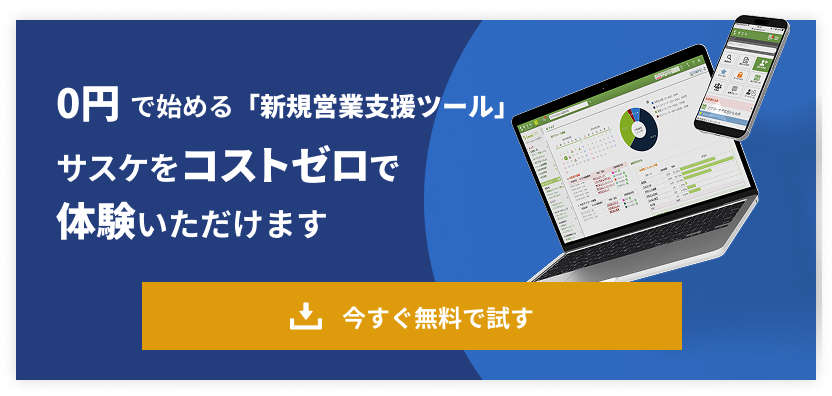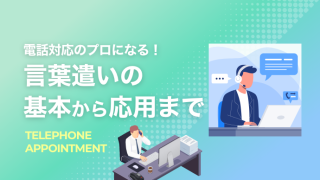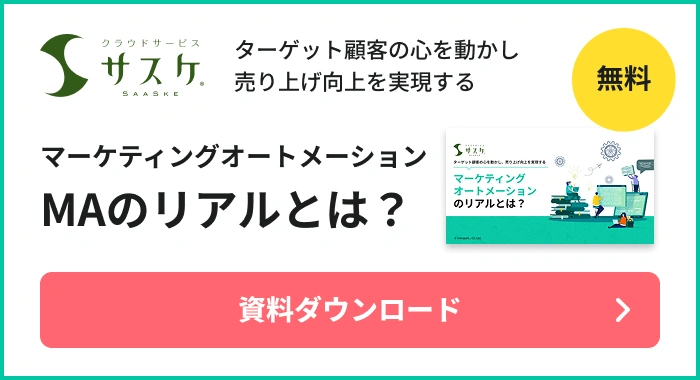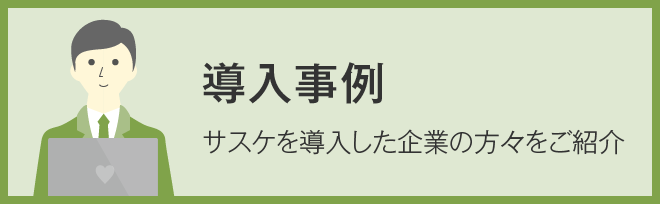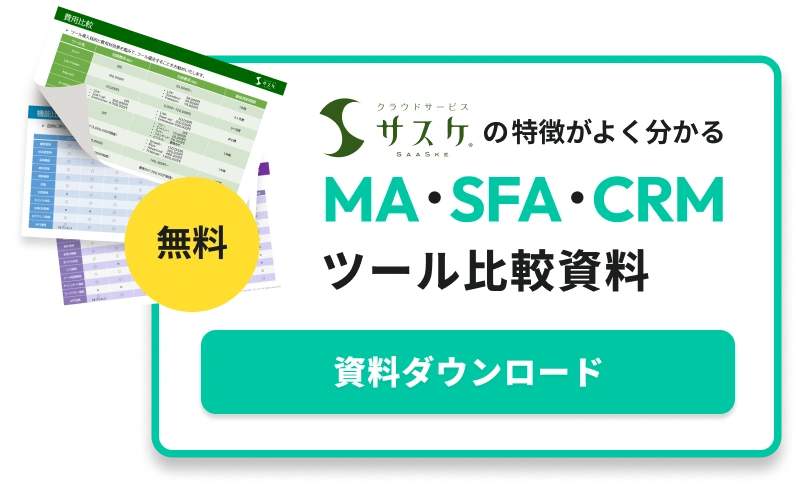SaaS(Software as a Service)の導入を検討する中で、最も気になるのが「導入コスト」ではないでしょうか。初期費用や月額料金はもちろん、実は見落としがちな「運用コスト」や「教育コスト」も、導入後の成果に大きく影響します。特に中小企業にとっては、「失敗できない投資」であるため、事前にどのような費用がかかるのか、どの程度のコストを想定すべきかを把握しておくことが極めて重要です。
本記事では、以下のポイントをわかりやすく解説します。
- SaaS導入にかかるコストの内訳と相場感
- 予算別に選べる導入モデルの特徴と違い
- 費用だけにとらわれない選定の視点
- 中小企業の成功事例と、具体的なサービス(クラウドサービス サスケ)の紹介
コストと効果のバランスを見極め、失敗しないSaaS導入を実現するためのヒントを、実践的な視点からご紹介します。
Contents
SaaS導入コストを事前に知っておくべき理由
中小企業にとって導入が“決断しづらい”背景とは
中小企業にとってSaaS導入は、「業務改善に役立つかもしれないが、本当に成果が出るのか不安」というジレンマを抱えた投資です。とくにExcelなどで業務を回してきた企業では、「今すぐ必要か?」という疑問と、「導入によってどれだけ業務が変わるのか?」という不透明感から、意思決定が進みにくい傾向があります。
また、営業やマーケティングなど複数部門にまたがるツール導入の場合、社内調整のハードルも高く、最初の一歩が踏み出しづらいという声もよく聞かれます。こうした中で導入を進めるためには、コストの全体像を明確に把握し、社内で共有できる資料や根拠を持つことが重要です。
金額だけでは測れない「隠れコスト」の存在
「月額〇円だから安い」と感じて導入したものの、実際には設定作業・社内教育・運用定着のためのサポートなど、目に見えないコストが積み重なっていたというケースは少なくありません。これが“隠れコスト”です。
特に社内リテラシーが高くない場合、「操作ミスによるトラブル」「定着しないまま放置」「追加サポートが発生」など、当初見積もっていなかった費用がかさみ、結果的に割高になることもあります。導入前にこれらを想定できていないと、「安く導入したのにコスパが悪かった」という結果に終わってしまいます。
SaaS導入にかかる費用項目とその目安
初期費用:導入準備や設定にかかるコスト
SaaS導入時にまず発生するのが初期費用です。これは、システムの初期設定・データ移行・アカウント開設・運用設計支援などにかかる費用で、ベンダーやサービスによって大きく異なります。無料のツールもありますが、導入支援やカスタマイズを含む場合は10〜50万円程度かかるケースも少なくありません。
特に中小企業では、「社内にIT担当がいない」「設定に不安がある」といった理由から、初期支援を外部に依頼するケースが多く、そのぶん初期費用が高くなりがちです。コストを抑えるためには、内製できる範囲と外部に任せる部分を見極めることが大切です。
月額費用:人数・プランで変動する利用料
SaaSの基本的な課金体系は月額課金(サブスクリプション)です。1ユーザーあたり月数千円〜1万円前後が一般的で、使いたい機能や管理ユーザー数に応じてプランを選びます。
たとえば、営業支援ツール(SFA)では「名刺管理+案件管理」などのシンプルな構成なら安価に利用できますが、マーケティング機能(MA)や外部連携を含む場合は中〜高価格帯になる傾向があります。
また、契約単位(年払い・月払い)や最低ユーザー数の条件も要チェックポイントです。
運用・サポート費:教育や社内対応の工数
見落とされがちなのが、運用・サポートにかかる“隠れコスト”です。導入したSaaSを活用するためには、社内向けの研修、マニュアル整備、ヘルプデスク対応などが必要となり、担当者の工数が無視できない負担になります。
また、「設定して終わり」ではなく、定期的な活用状況の見直し・KPI設定・レポーティング運用なども、継続的にコストが発生するポイントです。
この部分をあらかじめ見積もっておかないと、「安く始めたつもりが、手間と人件費がかさんで逆に高くついた」という事態にもなりかねません。
コスト別で比較するSaaS導入の代表モデル
SaaSは導入形態やサポート範囲によって、初期費用・月額コストが大きく異なるのが特徴です。ここでは、自社の予算や体制に合わせて選びやすいように、代表的な3つのモデルを比較します。
低価格プラン:最小限でスタートできるライト型
予算を最小限に抑えて始めたい企業向けのモデルです。初期費用ゼロ・月額1ユーザーあたり1,000〜3,000円程度のサービスも多く、名刺管理や簡易な営業支援などの用途で利用されます。
無料プランやトライアル付きのサービスもあり、小規模チームやテスト導入にも最適です。ただし、機能が制限されていたり、サポートがつかないケースが多いため、「SaaSをとりあえず試してみたい」段階の企業に向いています。
中価格プラン:外部支援つきのバランス型導入
一定の業務改善を狙いたい中堅企業向けのプランです。初期費用10万〜30万円前後、月額は1ユーザー5,000〜10,000円程度が目安で、外部サポートや導入支援付きのケースが多いのが特徴です。
この価格帯では、SFA(営業支援)やMA(マーケ支援)などの機能を一体型で提供するサービスも増えており、業務全体の効率化を狙えます。社内での設定・運用に不安がある企業にとっては、「導入から定着まで」を見据えた現実的な選択肢になります。
本格導入型:定着・活用まで支援するフルサポート型
業務プロセスの抜本的な見直しや、全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したい企業向けのモデルです。初期費用30万〜100万円以上、月額も高額になるケースがありますが、そのぶんカスタマイズや伴走支援、KPI設計まで含むケースが一般的です。
こうしたプランでは、外部パートナーによる導入コンサルティングがつくことも多く、「SaaS導入を成果につなげたい」という意志が強い企業にフィットします。ただし、費用対効果を高めるには、社内のリソース確保や目的の明確化が前提となるため、準備不足のまま始めるのはおすすめできません。
SaaS導入を成功させる「選定の考え方」
SaaSは「安く早く導入できる」ことが魅力ですが、自社に合わないツールを選ぶと、かえってコストや業務負荷が増えてしまうこともあります。ここでは、費用だけにとらわれない、本当に使えるSaaSを見極めるための視点を整理します。
費用以外に注目すべき3つの視点(業務適合性・成長性・サポート体制)
SaaSを選定する際は、次の3つの視点を意識することで、“安いけれど使えない”というリスクを避けられます。
- 業務適合性:自社の業務フローや既存ツールとスムーズに連携できるか?現場が実際に活用できる設計になっているか?
- 成長性:事業や組織の拡大に応じて、柔軟にプラン変更・機能追加ができるか?将来的にも使い続けられるか?
- サポート体制:チャット・電話・導入支援など、トラブル時に頼れる体制があるか?担当者不在でもスムーズに運用できる仕組みか?
これらを費用とセットで比較することが、導入後の“満足度”を左右します。
選定前に確認したい社内体制と導入目的の整理
ツールを探す前に、「なぜSaaSを導入したいのか?」という目的と、「社内でどこまで対応できるのか?」という体制を明確にすることが重要です。
たとえば、「営業案件を見える化したい」のか、「マーケティングから商談までの一気通貫の管理をしたい」のかで、選ぶべきツールは大きく変わります。また、社内に運用できる人材がいるか/誰が主担当か/どの部門を巻き込むかといった要素も、成功可否を分けるポイントです。
目的や体制が曖昧なままツールを選ぶと、機能が合わない・使われない・属人化するなどのトラブルにつながります。費用の比較に入る前に、“目的と現場”を棚卸ししておくことをおすすめします。
費用だけでSaaSを選ぶと失敗する理由
SaaSは「コストが安く見える」ことで導入ハードルが下がる反面、価格だけを基準に選んでしまうと、導入後に失敗するリスクが高くなります。ここでは、よくある失敗パターンを紹介しながら、なぜ費用以外の視点が重要なのかを解説します。
導入したが使われないツールになってしまう
「安いからとりあえず導入してみた」というケースで多いのが、現場が使わなくなってしまうという失敗です。
例えば、「機能が多すぎて複雑」「画面が見づらくて直感的でない」「営業メンバーが使い方を理解できない」など、現場との相性を無視した結果、使われないまま放置されることがあります。
結果として、導入コストも運用工数も無駄になり、現場の不信感を招くという悪循環に陥るリスクがあります。
社内に浸透せず、現場で混乱が起きる
SaaSは単なるツールではなく、業務フローそのものに影響を与える存在です。そのため、導入時に業務整理や社内調整が不十分だと、
「誰が入力するのか曖昧」「使い方が部門ごとにバラバラ」「誰も責任を持たない」といった状況が起こります。
特に中小企業では、一人ひとりの業務範囲が広く属人化しているため、SaaS導入によってかえって混乱するケースも少なくありません。費用の安さではなく、“社内で運用できるか”という視点が不可欠です。
業務効率化どころか、かえって手間が増える例も
「これまで紙やExcelでできていたことが、SaaSに置き換えたことで手間になった」
そんな声が出るのは、導入前に業務設計や運用ルールの整備がされていない場合です。
たとえば、入力項目が多すぎる、確認フローが複雑になる、既存のツールと連携できず二重入力になるなど、SaaSによって逆に業務が煩雑になることもあります。
こうした事態を防ぐには、価格だけでなく「運用設計のしやすさ」や「現場の目線」で選ぶことが不可欠です。
中小企業の成功事例に学ぶ、導入と費用の最適解
「うちの規模でも本当にSaaSで効果が出せるのか?」
そんな不安を抱える中小企業の方に向けて、実際に導入して成果を上げた企業の視点から、費用と効果のバランスをどう捉えるべきかを紐解いていきます。
成果につながった企業の「選定基準」と「導入ステップ」
成功した企業に共通するのは、「価格の安さ」ではなく、「自社に合うか」を軸にツールを選んでいた点です。
具体的には、次のような順序で導入を進めていました。
- 課題の明確化(例:営業の案件進捗が見えない、引き継ぎが属人化している)
- ツールの目的設定(例:営業情報の共有と定着を実現したい)
- 比較検討で重視した軸(例:使いやすさ・サポート・将来的な拡張性)
- 段階的な導入(スモールスタート→社内展開)
このプロセスを経ることで、コスト以上の価値を引き出す導入が実現しています。
SFA×MAの一体型ツールで無駄を省くには?
特に注目されているのが、営業支援(SFA)とマーケティング支援(MA)を一体化できるSaaSの活用です。
バラバラだったツールを一本化することで、以下のような無駄の削減と業務効率化が図れます。
- 情報の一元管理によって、案件の抜け漏れ・重複を防止
- ステップメールなどを自動化し、営業の工数を軽減
- 顧客データと行動履歴を統合し、ホットリードへのアプローチ精度が向上
このように、部門間の連携を前提に設計されたツールを選ぶことで、単体コストでは見えない“総合的な費用対効果”が高まるのです。
「クラウドサービス サスケ」の事例:段階導入でスムーズに定着
たとえば、営業とマーケティングの連携強化を目的に「クラウドサービス サスケ」を導入した中小企業では、段階的な導入と柔軟な運用設計によって、着実な成果につなげています。
初期は営業リストの一元管理とメール配信からスタートし、次第にステップメールや商談分析の活用へと展開。最初から全機能を使いこなすのではなく、必要に応じて段階的に広げていくことで、現場への定着率が高まりました。
また、サスケはSFA×MAを一体で提供しているため、別々にツールを契約するよりもコストを抑えやすく、運用負荷も少ないという声が多く聞かれます。
コストと効果のバランスを重視する中小企業にとって、“等身大で導入しやすい選択肢”として注目されています。
SaaS導入コストに関するよくある質問
SaaS導入を検討している担当者の多くが、費用にまつわる疑問や不安を抱えています。このセクションでは、実際によく寄せられる質問をもとに、導入前に押さえておきたいポイントをQ&A形式で解説します。
無料ツールと有料ツール、どこが違うの?
無料ツールは導入しやすい反面、機能やサポート体制が制限されているケースが大半です。たとえば、
- ユーザー数や登録件数に制限がある
- 外部連携やカスタマイズができない
- トラブル時の対応が自己解決に限られる
など、業務が拡大したときにすぐ限界が来る可能性があります。
一方、有料ツールは継続的な運用や定着を前提とした設計がされており、長期的に使い続けることを想定しているのが大きな違いです。
「いま無料で始めるか」ではなく、「将来どこまで活用したいか」で選ぶことが大切です。
人件費や設定作業などの間接コストはどう見る?
SaaS導入には、ツールそのものの費用だけでなく、社内の担当者が費やす時間や作業コストも大きく関係します。
たとえば、
- 初期設定やデータの移行作業
- 社内向けのマニュアル作成や研修実施
- 運用ルールの整備・社内からの問い合わせ対応
これらの作業に週5〜10時間かかるケースも珍しくありません。
もし「専任で対応できる人がいない」「運用設計に自信がない」場合は、導入支援や伴走サポートがあるSaaSを選ぶことで、間接コストを抑える効果も期待できます。
補助金や助成金は活用できる?申請の注意点は?
はい、多くの自治体や支援機関では、SaaS導入や業務のデジタル化を対象とした補助金・助成金制度が用意されています。
たとえば、IT導入補助金や中小企業デジタル化応援事業などが該当するケースです。
ただし、
- 申請期間が限定的であること
- 対象ツール・業者が指定されている場合があること
- 事前申請が必要で、契約・支払い後では対象外となること
など、申請のタイミングや条件を見誤ると補助が受けられないリスクもあるため、必ず早めに情報収集しておくことが重要です。
必要に応じて、ツール提供会社が補助金申請のサポートをしてくれる場合もあるため、導入前に相談してみるとスムーズです。
明日から使える!SaaS選定3つのポイントまとめ
- 目的と体制を明確にすること
SaaSを導入する理由(例:営業プロセスの可視化、リード一元管理、属人性の解消など)を具体化し、運用できる組織体制を事前に整理しましょう。 - 価格だけで判断せず、「運用負荷」や「定着性」も重視すること
月額や初期費用だけで選ぶと、設定工数や現場の負荷で苦しくなる可能性があります。自走できるかを意識した設計かどうかも見るべきです。 - 必要に応じて外部支援やツール連携を活用すること
社内だけで運用するのが難しい場合は、導入支援や連携機能が整ったツールを選ぶと導入がスムーズになります。
これらをふまえ、「価格だけで選ばない」「現場目線の導入設計を重視する」視点を持ってSaaSを選定すれば、導入後の失敗リスクを大きく下げられます。
SaaS選定を“成果につながる基盤”に変えたいなら、サスケ
SaaS選びで失敗しやすいのは、機能や価格だけで決めて、現場運用が追いつかず使われなくなるケースです。
クラウドサービス サスケ は、選定段階から導入後の定着までを見据えた設計と支援体制で、成果につながるSaaS活用を支えます。
- 顧客/リード/商談・メール施策を SFA+MAの一体型 で扱え、ツールが分断しない
- UI/操作性を重視し、現場メンバーが抵抗なく使える設計
- AIによるスコアリングや優先提案で、効率と精度を両立
- 活動データを可視化できるダッシュボードで、定着効果を見える形に
- スモールスタート対応で、段階的に導入できる構成
- 導入支援・定着フォローが充実し、初期運用時の負荷を軽減
SaaS導入を“投資”ではなく“成果を生む変革”にしたいなら、サスケはその最適な選択肢のひとつになります。
まずは無料デモ・資料請求で、現場にフィットする使い勝手と効果をご体感ください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。