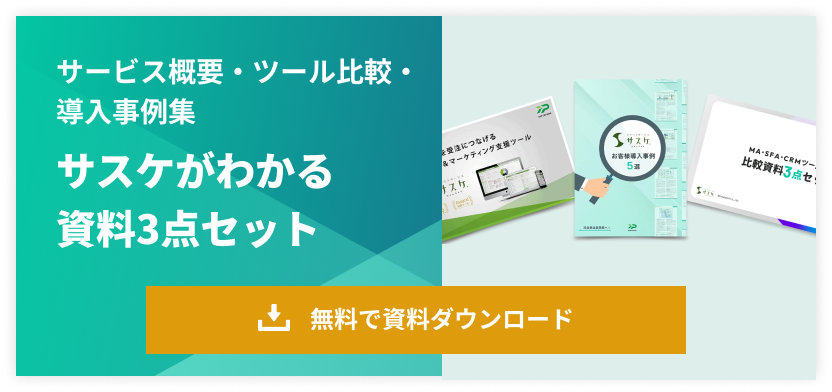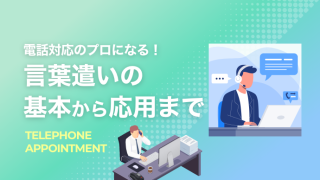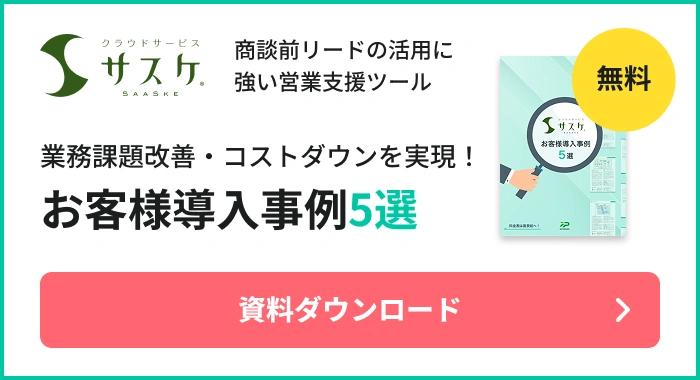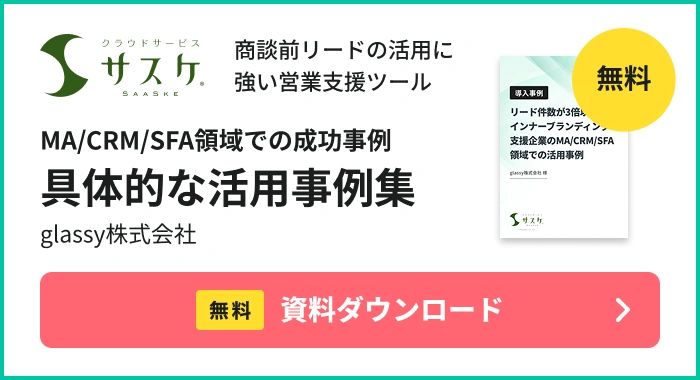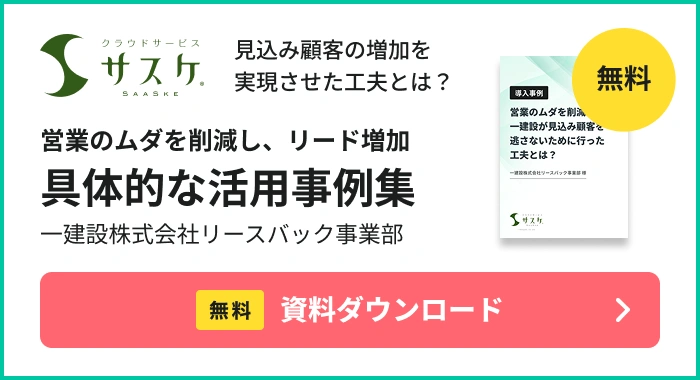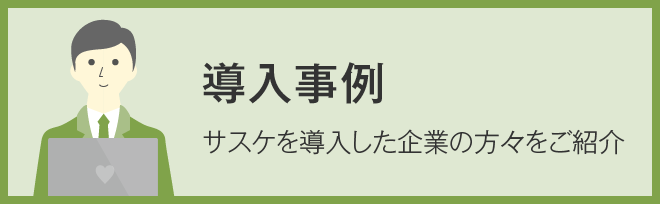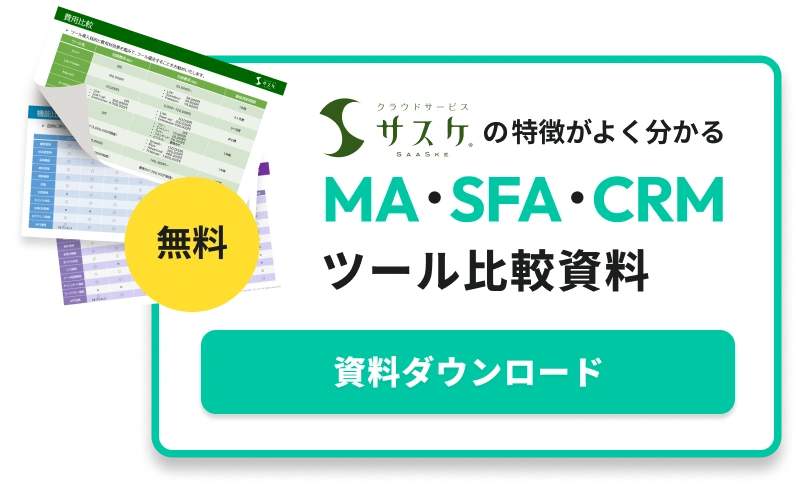「Slackでも連携してるし、議事録も残してる。なのに、なぜか伝わっていない。」
そんな悩みを抱えたまま、日々の業務に追われていませんか?
情報共有の手段はあふれている現代ですが、“伝える仕組み”が機能していなければ意味がないのです。
ここでは、なぜ「共有しているのに伝わらない」のか、その根本原因を紐解きます。
Contents
なぜ情報共有は“しているのに”伝わらないのか?
情報が「分散」していることが最大のボトルネック
あなたのチームでは、以下のようなことが起きていませんか?
- 資料はGoogleドライブ、議事録はメール、進捗はSlack、タスクは別ツール
- 「あの情報どこだっけ?」と検索に数分〜数十分かかる
- 最新のファイルがどれかわからず、複数人が古い資料を参照している
これらはすべて、「情報が分散している」ことによる弊害です。
情報のありかがバラバラで、アクセスまでに手間がかかる。結果として、伝達コストが上がり、重要な連携ミスが生まれます。
「伝える側」と「受け取る側」で目的がズレている
情報共有の場面では、送り手と受け手の“目的意識”がズレていることも少なくありません。
たとえば、送る側は「とりあえず議事録を残した」と満足しても、受け取る側からすれば「長文すぎて読む気がしない」「どこが重要か分からない」と感じてしまう。
情報は“届け方”次第で価値が変わるのです。
受け手の立場を考え、「何を・誰に・どのくらいの粒度で伝えるか?」を意識するだけで、情報の伝達効率は劇的に変わります。
情報共有を効率化する3つの原則
「情報共有を改善したい」と思ったとき、やみくもにツールを増やしたり、テンプレを整えたりするのはNGです。
まずは情報共有の“土台”となる3つの原則を理解しましょう。
① 情報の“居場所”を固定する
最もシンプルで効果的なのが、「どんな情報を、どこに置くか」を明文化することです。
- 議事録 → Notionの「議事録」セクション
- 顧客情報 → Googleスプレッドシート内の「取引先リスト」
- プロジェクト進捗 → Trelloボード or Backlog
「この情報ならここを見ればいい」とチーム全員がわかる状態にすれば、探すストレスはなくなります。情報の迷子をゼロにすることが最初の一歩です。
② ツールの役割を明確にする
便利だからといって、何でもかんでもSlackやGoogleドライブに投げ込むと、結果として混乱を招きます。
- Slackは“今この瞬間の共有”用
- Notionは“情報を蓄積・構造化する”用
- Googleドライブは“ファイル保管と共有”用
というように、ツールの役割を分けるルール作りが大切です。これにより、「あの情報、どこに書いたっけ?」を防げます。
③ 更新・通知の自動化で抜け漏れを防ぐ
効率化において重要なのが「自動化」です。
毎回「〇〇更新しました」と手動で通知するのではなく、ツール連携(例:Slack連携やZapierなど)を活用して自動通知を設定しましょう。
例:
- Notionで議事録が更新されたらSlackに通知
- Googleフォームの回答が来たらスプレッドシートとメールに反映
こうした「人手に頼らない仕組み」こそが、持続可能な情報共有を実現するカギです。
実践編|よくある課題とその解決法
日々の業務において、情報共有の“つまずきポイント”は意外と共通しています。
ここでは、実際によくある課題とその具体的な解決策をセットで紹介します。
議事録が読まれない → サマリー形式+Slack連携
議事録は書いたけど、誰も読んでいない──。これは非常によくある問題です。
原因:
- 長文で読みづらい
- どこが重要かわかりにくい
- 保管場所が共有されていない
解決策:
- 議事録は3行サマリー+詳細構造のハイブリッドにする
例:「本日の決定事項」「次回のToDo」「懸念点」の3項目だけ先に記載 - Slackと連携し、更新時に該当チャンネルに自動通知
- Notionなどを使って、議事録テンプレを共通化
資料が探せない → タグ&命名ルール統一
資料を探す時間=非生産時間です。
「Googleドライブで“最終版”って10個あるんですけど…」という状況、ありませんか?
解決策:
- ファイル名に日時・カテゴリ・バージョンを入れる(例:2025_06_定例議事録_v2)
- タグやラベル機能を活用(Googleドライブのスター、Notionのタグ列)
- ドライブ構成を「プロジェクト→用途→日付」のように統一
ポイントは、“未来の自分やチームメンバーが見てすぐ理解できる”ことです。
情報がタイムラインに埋もれる → 週次の再通知設定
SlackやTeamsのタイムラインに流れた情報は、見逃されやすい。
1日2日で情報価値がなくなるのは、非常にもったいない話です。
対策案:
- 重要情報は週次で「まとめ投稿」する(自動化ツールを使えば楽)
- たとえば「今週の重要トピック5選」などを毎週金曜に流す
- Slackのピン留め、Notionの「今週の共有事項」ページも有効
このように「何度も見せる」「場所を固定する」ことで、情報定着が進みます。
Slack・Notion・Googleドライブの最適な使い分け方
便利なツールを導入しても、役割がかぶっていたり、誰も使いこなせていないのでは本末転倒です。
ここでは、チーム内の代表的3ツールの“棲み分け”ルールを紹介します。
リアルタイム vs. 蓄積型でツールを選ぶ
まず前提として、情報には2種類あります。
- 即時性が重要な「今の話」→ SlackやTeams
- 長期的に保管・参照すべき「記録」→ NotionやGoogleドライブ
Slackだけで完結しようとすると、「あの話どこいった?」となりがちです。
一方で、Notionにすべて書くと“死蔵情報”になりがち。
どの情報を、どのツールに残すかを明確に設計しましょう。
連携ツールを使ってワンクリック共有を実現
情報共有の効率化において、「手動操作を減らすこと」も極めて重要です。
おすすめ施策:
- SlackとGoogleドライブを連携し、「/drive」で即シェア
- NotionページにSlack通知を連携して更新を知らせる
- ZapierやMakeを使って「情報入力 → 自動通知」の仕組みを作る
こうした「半自動ルーティン」があるだけで、“共有忘れ”や“確認漏れ”は大幅に減ります。
すぐに使える!情報共有の改善チェックリスト
本記事の内容を踏まえて、「情報共有の効率化」が実践できているかを確認できるチェックリストを用意しました。
| No. | チェック項目 | 状況 | 対策ヒント |
| 1 | 各情報の「置き場所(保存場所)」がチーム全体で明文化されている | □ | ルールを文書化し、共有ページに固定表示する |
| 2 | 「誰が、何を、いつ」更新したかがすぐに把握できる仕組みがある | □ | 通知の自動化、履歴管理の見える化が有効 |
| 3 | ファイル名や資料タイトルに、日時・内容・バージョンなどが統一ルールで記載されている | □ | 「YYYYMMDD_内容_v1」など命名ルールの徹底 |
| 4 | 議事録や日報は“3行サマリー+詳細構造”で書かれていて、必要な情報がすぐ把握できる | □ | 要点を先に書く、テンプレートの活用 |
| 5 | Slack・Notion・ドライブなど、ツールごとの「役割分担」が整理されている | □ | ツールの目的別マップを作成・共有 |
| 6 | チームの誰でも、過去の資料や対応履歴を“数クリック”で探し出せる状態になっている | □ | サスケなどの一元管理ツール導入も検討 |
| 7 | 「確認漏れ」や「対応抜け」が、過去に何度も発生している | □ | 通知・アラートの自動化とToDo化が必要 |
| 8 | 情報の重要度・優先度が明確にされており、「どれを読むべきか」が判断できる | □ | アイコンやセクション区切りなどの工夫 |
| 9 | 運用ルールやマニュアルが「属人化」せず、誰でもアクセス・更新できるようになっている | □ | マニュアルの定位置管理+更新フロー整備 |
| 10 | 社内での情報共有方法について、半年以内に見直し・改善を実施したことがある | □ | 定期的な運用レビューで“形骸化”を防ぐ |
5項目以上チェックがつかない場合 → 情報共有の運用に課題あり
7項目以上チェックの場合 → チーム運用は安定化傾向、さらに自動化・統合の余地あり
全チェックチェック+属人性なし → 理想形。ただしツール統合でさらなる効率化を目指せる
となります。参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1:情報共有の効率化って結局何から始めればいいの?
A:まずは「情報の置き場」を固定することから始めましょう。
「誰が、どこに、どんな情報を置くか」を可視化するだけで大きな改善につながります。
Q2:ツールが多すぎて逆に非効率では?
A:ツールは「使い分け」さえ明確にすれば、むしろ効率化の武器になります。
不要なツールを絞る、役割を重複させないなど、定期的な棚卸しがカギです。
Q3:ルールを浸透させるにはどうすれば?
A:まずはシンプルなルールから始めて、「なぜそのルールがあるのか」をセットで伝えること。トップダウンだけでなく、現場メンバーの合意形成があると継続しやすくなります。
まとめ|情報共有の効率化は「仕組み+運用ルール」で実現しよう
情報共有はツールを導入するだけでは“見せかけ”に留まりがちです。
「情報の居場所を明確にする」「ツールの役割を整理する」「更新・通知の自動化を取り入れる」という3つの原則を意識して設計すれば、チームのコミュニケーションは飛躍的に効率化します。
ただし、仕組みを作って終わりではなく、「現場が使いやすく続けられる運用ルール」まで設計・改善を重ねてこそ、真に伝わる情報体制が生まれます。
情報共有を“散らからず使われる基盤”にしたいなら、サスケ
情報が分散して、どこに何があるか分からなくなっていませんか?
クラウドサービス サスケ は、情報共有のムダを排除しながら、営業・対応履歴・案件情報までを一元的に扱える基盤を提供します。
- 顧客・商談・対応履歴を情報源と一緒に管理し、散逸を防止
- 更新・通知の自動化機能で、手動通知の手間と抜け漏れを削減
- タグやステータス管理で情報を構造化し、「探す負荷」を減らす設計
- アクセス権限や閲覧ログにより、情報の整合性・信頼性を保つ
- スマートな UI/操作設計で、現場が違和感なく運用できる
情報をただ「共有された状態」で止めず、「伝わり、活かされる体制」に変えたいなら、サスケを活用して情報の“見える化+活用”を始めてみてください。
無料デモ・資料請求で、その使いやすさをご体感いただけます。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。