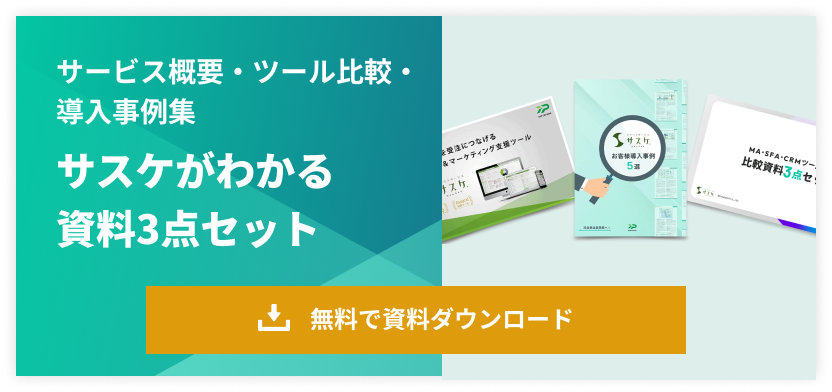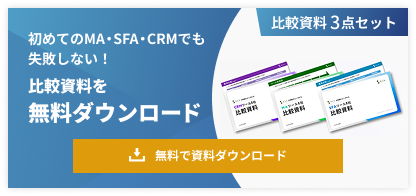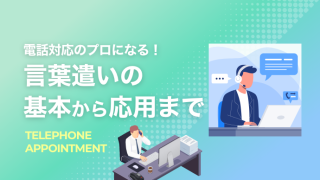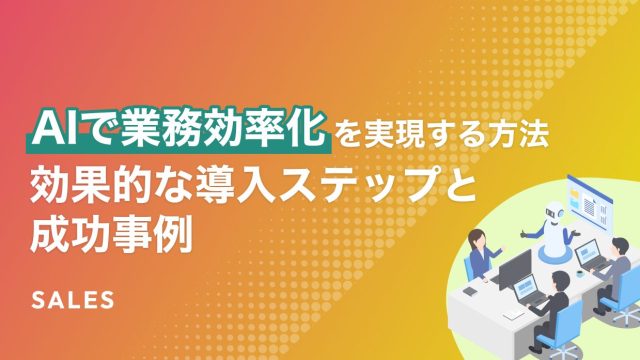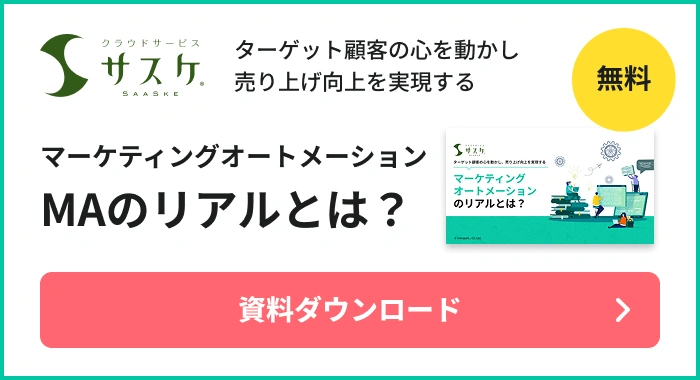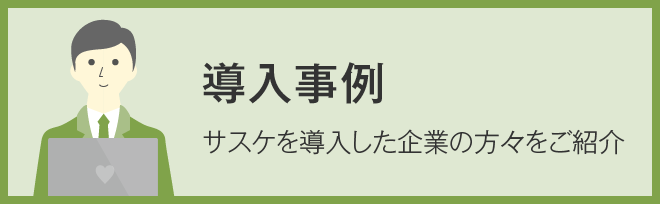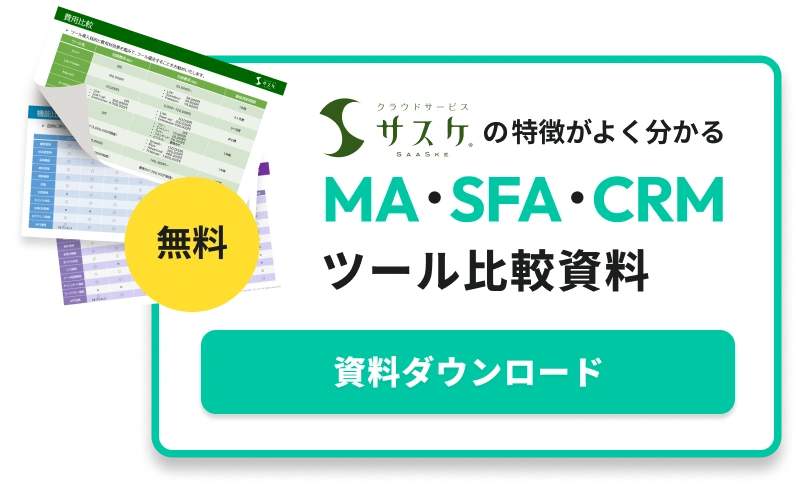「社内の情報が特定の人にしか共有されていない」「引き継ぎのたびにドキュメントが散在して困る」
そんな悩みを抱える企業にとって、ナレッジ共有ツールの導入は急務となりつつあります。
業務マニュアル、成功事例、過去のトラブル対応など、日々の業務で蓄積される“知識資産”を可視化・共有することで、業務の効率化や教育の質が向上します。
本記事では、主要なナレッジ共有ツールの特徴や比較ポイントを解説しながら、自社に合った最適な選び方を丁寧にご紹介します。
後半では、営業現場でも活用されているクラウドサービス サスケの実例も取り上げますので、ツール選定で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
Contents
ナレッジ共有ツールの基本機能と導入目的
情報の属人化を防ぐ仕組み
ナレッジ共有ツールの最大の役割は、「あの人しか知らない」をなくすことです。
特定の社員にしか分からない業務ノウハウが放置されると、退職や異動時に情報が失われたり、トラブルの再発を防げなかったりします。
そこで、社内に蓄積されるナレッジを誰でもアクセス可能な仕組みとして記録・検索できる環境を整えることが、属人化を防ぐ第一歩となります。
Q&A形式で共有できるツールや、投稿にコメントできる機能を活用すれば、知識が「一方通行」で終わらず、組織内で育つ文化も醸成できます。
業務の引き継ぎ・育成にも役立つ
新人育成や異動者への引き継ぎでも、ナレッジ共有ツールは大きな効果を発揮します。
過去の事例や社内ルールが体系的に残っていれば、教える側の負担が減り、教わる側もスムーズに業務をキャッチアップできます。
特に、検索性や更新履歴がしっかりしているツールを選べば、古い情報と新しい情報の混在を防げるため、運用ミスのリスクも大幅に減少します。
属人化を防ぐだけでなく、「育てる・受け継ぐ」仕組みとしてもナレッジ共有ツールは有効なのです。
ナレッジ共有ツールの選び方
検索性・UIのわかりやすさ
ナレッジ共有ツールを選ぶうえで、最も重視すべきなのが“検索性”と“画面のわかりやすさ”です。
どれだけ情報が蓄積されていても、必要な情報にすぐアクセスできなければ意味がありません。タグ検索や全文検索、フィルター機能などを備えているかは、必ず確認しましょう。
また、UI(ユーザーインターフェース)が直感的であることも、日常的に使われるツールになるかどうかの分かれ目です。「誰でも使える」ことは、浸透の鍵となります。
ツール連携・通知機能
ナレッジ共有ツールは、単体で使うだけでなく、SlackやGoogle Workspace、Teamsなどと連携してこそ真価を発揮します。
たとえば、Slackに新しいナレッジの投稿通知が届くようにすれば、わざわざツールを開かなくても情報が自然と届く設計が可能です。
ツール連携が豊富なものを選ぶことで、他の業務ツールとの連携による自動化やワークフロー改善にもつながります。
情報の更新性と履歴管理
ナレッジは一度書いたら終わりではありません。情報は常にアップデートされ、最新の状態が正しく共有されていることが重要です。
そのため、「誰が・いつ・どこを更新したか」が明確に分かる履歴管理機能を備えているツールが望ましいです。
さらに、旧バージョンに戻せる「バージョン管理」ができると、間違って書き換えてしまった場合も安心です。
社内定着のしやすさ
どれだけ高機能なツールでも、社内に定着しなければ意味がありません。
操作が難しかったり、投稿ルールが複雑すぎると、誰も使わなくなってしまいます。
そのため、導入時は「投稿しやすい仕組み」「活用事例の共有」「推進役の設置」など、使ってもらう工夫がセットで必要です。
定着しやすいツールには、初期設定が簡単・テンプレートが充実・チュートリアルがわかりやすい、などの共通点があります。
料金とサポート体制
料金体系も比較のポイントです。1ユーザーあたりの月額費用、無料トライアルの有無、初期費用などを確認しましょう。
また、社内で困ったときにすぐ問い合わせできるように、サポート体制が整っているかも要チェックです。
導入から定着までをサポートしてくれるベンダーであれば、はじめての導入でも安心して進められます。
代表的なナレッジ共有ツール5選
Notion|自由度が高いが運用設計がカギ
自由度が非常に高く、ドキュメント・データベース・タスク管理まで一元化できるのがNotionの特長です。テンプレートのカスタマイズ性も高く、チームごとに柔軟な運用が可能です。
一方で、あまりに自由すぎるため、「何をどこに書くか」のルールを明確にしないとナレッジが散らかってしまうという課題も。情報共有の文化や運用ガイドラインの整備ができるチームにおすすめです。
Confluence|大規模・エンジニア寄りのチームに適する
Atlassian社が提供するConfluenceは、エンジニアや開発チームとの相性が良く、Jiraとの連携でプロジェクト管理とナレッジ共有をシームレスに行えます。
ページ構成がしっかりしており、階層化やアクセス権管理も細かく設定可能。中〜大規模組織や情報統制を重視する企業に向いています。
ただし、UIにややクセがあり、非IT部門では最初に戸惑うことも。社内に技術寄りのユーザーが多い場合に特に活用しやすいツールです。
Qast|Q&Aベースで属人化防止に強い
「質問→回答」の形式でナレッジが蓄積されるのがQastの最大の特徴。普段の疑問や相談をそのままナレッジに変換できるため、投稿のハードルが低く、自然と情報がたまる仕組みが魅力です。
属人化防止や引き継ぎ効率化に効果的で、Slack連携など通知機能も充実。「まずは気軽にナレッジ文化をつくりたい」企業に最適な選択肢です。
NotePM|階層化・マニュアル管理に強み
NotePMは、マニュアルや議事録など“構造化された情報”を整理して残したい企業に特に人気の高いツールです。フォルダ階層が分かりやすく、社内Wikiとしても使いやすい設計になっています。
Markdownやファイル添付、更新履歴管理などの基本機能が充実しており、「情報を整理して残す」ことに強みがあります。導入や操作もシンプルで、非IT系の部門でも扱いやすいのもポイントです。
TUNAG|制度・ノウハウ共有に特化した社内SNS型
TUNAGは、社内制度や取り組み、社員のナレッジを可視化・共有できるSNS型のツールです。人事施策や社内イベントの活用状況も一元管理できるため、エンゲージメント施策とも相性が良いです。
投稿やリアクションなどのインタラクション要素が強く、「交流×ナレッジ共有」で企業文化の醸成を図りたい場合におすすめです。
ナレッジだけでなく、社内の温度感を可視化したい企業にとっては有力候補といえるでしょう。
業務の共有と可視化を実現したサスケの活用事例
営業チームの成功事例をナレッジ化
営業部門では、個人のノウハウや成功パターンが属人化しやすく、他メンバーに展開されないまま埋もれてしまうケースが少なくありません。
そこで注目されているのが、営業支援(SFA)と情報共有機能を兼ね備えた「クラウドサービス サスケ」の活用です。
サスケでは、商談の進捗や対応履歴に加え、過去の成功事例・提案内容・顧客の反応をコメントやメモとして蓄積可能。
これにより、ある営業担当が成果を出したプロセスが“見える化”され、チーム全体の共有知として活用できるようになります。
さらに、対応の質が高かった事例を「共有ナレッジ」として残せば、後輩育成にも役立つなど、営業活動におけるPDCAの高速化にもつながります。
属人化解消と育成スピードの向上を両立
サスケを導入した企業では、属人化していた営業ノウハウが蓄積・共有され、新人や中途入社メンバーの立ち上がりスピードが大きく向上した事例もあります。
特定の人の経験に頼らず、誰でもアクセスできるナレッジベースを日常業務の中で無理なく構築できる点が、サスケの強みです。
また、営業だけでなくマーケティングやカスタマーサポートとも連携して使えるため、部門横断での情報共有にも活用可能です。
ツールを切り替えることなく、一つのプラットフォームで“業務情報”と“ナレッジ”を同時に可視化・定着できる点が、他のナレッジツールにはない大きな利点です。
ナレッジ共有ツールに関するよくある質問
無料で使えるナレッジツールはある?
はい、いくつか存在します。たとえばNotionやConfluenceは、無料プランから始められるため、初期コストを抑えて試したい企業には有力です。
ただし、無料プランではユーザー数や機能制限がある場合が多いため、本格運用を視野に入れるなら有料プランとの比較もおすすめです。
また、Googleドキュメントやスプレッドシートなどを活用して、無料で簡易的なナレッジ管理を始めるケースもありますが、蓄積や検索・権限管理などに課題が出やすいため、中長期的には専用ツールへの移行が現実的です。
導入しても使ってもらえないときはどうする?
最も多い失敗パターンが「入れたら終わり」になってしまうことです。ツールがあるだけでは、社内の誰も使いません。
そのためには、以下のような工夫が必要です。
- 最初に運用ルールをしっかり整備する
- ナレッジ投稿をKPIに組み込む
- 使ってくれた人を称賛・可視化する仕組みを入れる
また、現場のキーマンや管理職が「まず使って見せる」ことも文化づくりには不可欠です。ツールそのものだけでなく、運用面の設計と浸透施策が成否を分けます。
NotionとQastはどう使い分ければいい?
NotionとQastは性質が異なるため、目的によって使い分けることが可能です。
- Notionは構造的に情報をまとめたいときに向いています。 たとえば業務マニュアルやプロジェクト進捗の共有、リソースの一元管理などです。
- Qastは「現場の声」や「日々の質問・回答」を自然とナレッジ化したい場合に強みがあります。
つまり、体系的に整理したいならNotion、カジュアルにナレッジを貯めたいならQastというのが基本的な考え方です。
最近では、両者を併用している企業も増えており、「構造化×日常会話型ナレッジ」の両輪で活用するケースも一般的です。
自社の課題に合ったツールを見極めて導入を
完璧なナレッジ共有ツールを探し続けるよりも、自社が「本当に必要としている機能」で使われるかどうかを軸に選ぶことが成功への近道です。
導入しやすさ、検索性、定着性、そして何より現場が「自然と使いたくなる」設計かどうかを重視して絞り込みましょう。
ツールの機能一覧に振り回されるのではなく、自社の情報共有課題を解決できる構成と運用設計を重視した選定こそが、現場定着と成果活用への第一歩です。
ナレッジ共有を“営業現場で使われて育つ仕組み”にしたいなら、サスケ
ナレッジ共有ツールを導入しても、情報が放置されがちなのは、業務ツールと分断して運用されるケースが多いためです。
クラウドサービス サスケ は、営業/対応履歴とナレッジを融合させた設計で、情報が自然にストック・活用される環境を提供します。
- 営業ログや対応メモがそのままナレッジとして蓄積され、別ツールに書き写す手間が不要
- タグ付け・全文検索・履歴管理により、必要な情報を即座に引き出せる
- 権限設定やアクセス管理で、情報の信頼性と安全性を確保
- UI/UXを重視した導線設計で、日常業務に“溶け込む”使いやすさ
- 部門横断の情報も統合でき、営業だけでなくマーケティング・サポート・管理部門でも活用可能
情報が増えるほど散らかる、共有されても活用されない…そんな悩みがあるなら、サスケで情報の“見える化 × 活用化”を始めてみてください。
無料デモ・資料請求で、現場で使えるナレッジ基盤の感触をぜひお確かめください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。