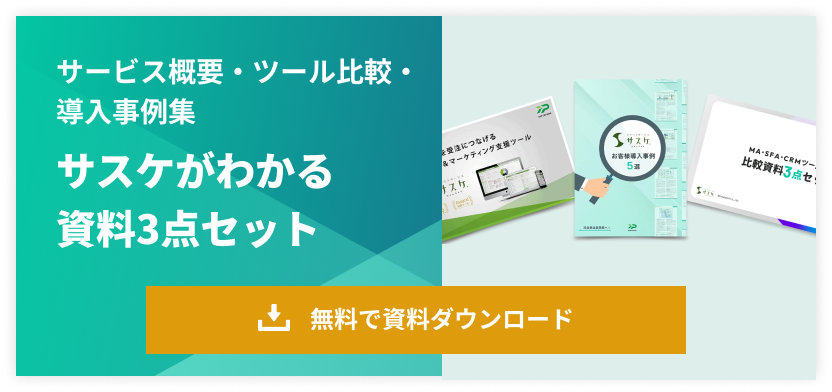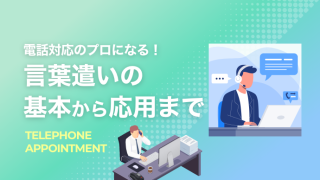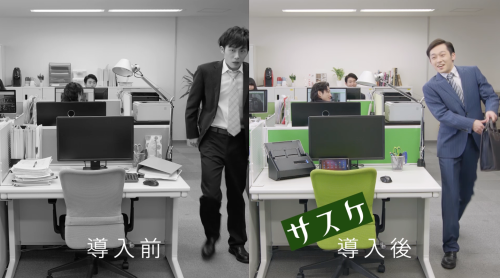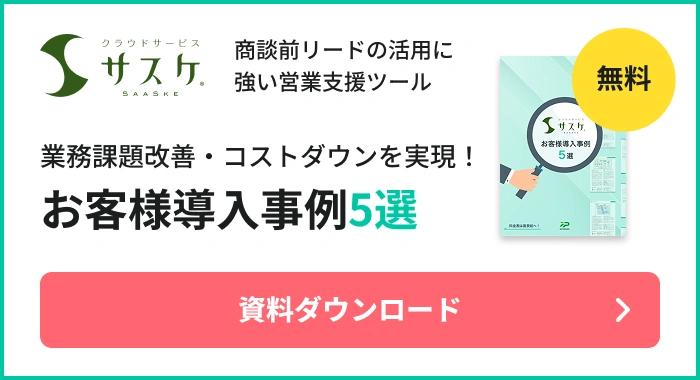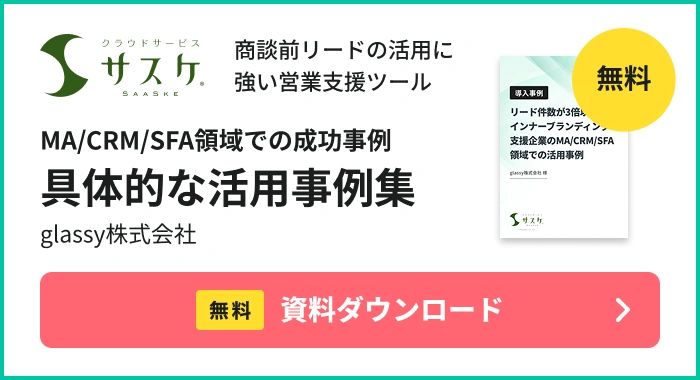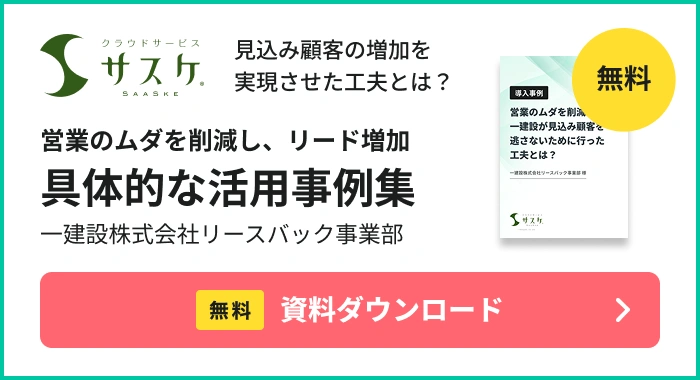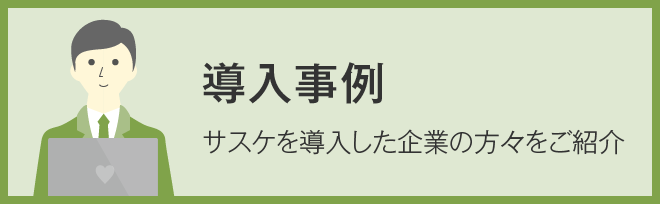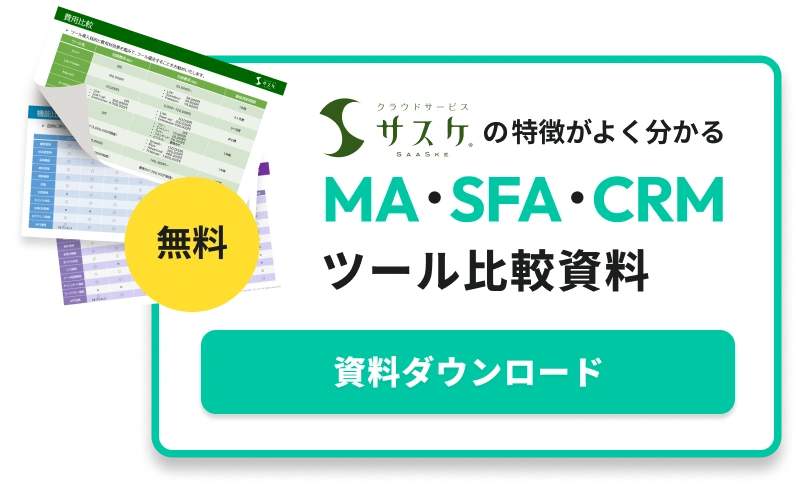「社内DX」という言葉を耳にする機会が増えてきたものの、具体的に何を意味し、どのように進めればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。特に中小企業や現場主導の組織では、ITツールを入れただけでは何も変わらないという悩みがつきものです。本記事では、「社内DXとは何か?」という基本から、実際の成功事例・よくある失敗・具体的な進め方まで網羅的に解説します。初めてDXを推進する担当者でも理解しやすいよう、現場目線で整理しました。
Contents
社内DXとは?意味と定義をわかりやすく解説
DX=IT導入ではない?本来の意味とは
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と聞くと、新しいシステムやツールを導入すること=DXと考えてしまいがちです。しかし、DXの本質はそこにはありません。経済産業省によると、DXとは「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を変革し、競争優位性を確立すること」と定義されています。
つまり「社内DX」とは、自社の業務や働き方をデジタルの力で根本から見直す取り組みです。ただ便利なツールを使うのではなく、“どの業務をどう変えるか”という視点が不可欠です。
「社内DX」が注目される背景
近年、急速な市場変化・人手不足・働き方の多様化といった課題が、企業の内部に大きな影響を及ぼしています。これまでのやり方では通用しないと感じ始めた現場が、「社内から変わらなければいけない」とDXを模索するようになったのです。
特に中小企業では、紙やExcel中心の業務がボトルネックになりやすく、属人化や情報の分断といった問題が表面化しがちです。こうした課題を組織全体で見直し、再設計することが“社内DX”の第一歩となります。
社内DXが必要とされる理由
中小企業の課題とDXの相性
中小企業の多くが抱える悩みとして、慢性的な人手不足、業務の属人化、情報共有の非効率が挙げられます。たとえば、特定の社員しか分からない業務があったり、報告や共有が紙や口頭で行われていたりと、非効率な体制が当たり前になっているケースは少なくありません。
こうした状態では、社員の入れ替わりや緊急時に業務が滞るリスクが高まります。しかし、すべての業務をシステム化・自動化するのは現実的ではないと感じている経営者や現場担当者も多いでしょう。だからこそ、無理のない範囲で一部業務から“見える化”や“共有の仕組み化”を進められるDXは、中小企業にこそフィットする取り組みなのです。
コロナ禍・人手不足・属人化…変革のタイミング
2020年以降のコロナ禍によって、出社を前提とした働き方が大きく揺らぎました。リモートワークやハイブリッド勤務が広がる中で、「情報共有ができない」「会わないと指示が伝わらない」といった問題が浮き彫りになり、これまで見過ごされていた業務課題が顕在化しました。
また、ベテラン社員の退職や若手の早期離職といった人材の流動化も進んでおり、“誰かがいないと回らない業務”をなくすことが急務となっています。こうした背景もあり、業務フローや組織構造を再設計する契機として社内DXを導入する企業が増加しています。
社内DXの進め方|現場が動く5ステップ
①業務棚卸しで現状を見える化
社内DXを成功させる第一歩は、現場の業務を“棚卸し”することです。現在、誰が・どこで・どんな作業をしているのか、手作業で行っている業務や重複している作業がないかを整理します。
この段階では、改善や効率化よりも「実態を正確に把握すること」が重要です。現場の協力を得ながら、属人化している業務やアナログ作業をリストアップしましょう。
「業務が多すぎて把握しきれない」という場合には、業務日報や月次レポートなどの既存資料から読み取るのも有効です。可視化された業務情報は、以降のDX設計の土台になります。
②小さく始めて改善するPDCA設計
社内DXは、いきなり全社で一斉に導入する必要はありません。むしろ、一部のチームや業務に絞って“小さく始めて、改善しながら広げる”アプローチが現実的です。
最初は、負荷が高く成果が見えやすい業務を対象にすると、チーム内での評価も得やすくなります。そして、改善施策の効果を評価し、必要に応じて修正しながら次の業務へと展開します。
このように、PDCA(計画・実行・評価・改善)の視点でDXを設計することが、長期的な定着につながる鍵となります。
③ツール選定のポイント
DXを進める上で避けて通れないのが、「どのツールを使うか」という選択です。ただし注意したいのは、機能の多さより「現場で使えるかどうか」の視点で選ぶこと。
現場が難しく感じたり、導入が面倒だったりすると、定着せずに形だけのDXになってしまいます。
たとえば、営業部門であれば顧客情報・商談履歴・対応履歴などを一元管理できるSFA(営業支援ツール)が有効です。これにより、情報共有や進捗管理が属人化せず、チーム全体での動きが見えるようになります。
おすすめ:クラウドサービス サスケによる情報一元管理
クラウドサービス サスケは、顧客情報・営業履歴・対応記録をまとめて管理できる営業支援ツールです。
属人化しがちな営業活動を“チームで共有できる資産”として蓄積し、ナレッジ化・引き継ぎ・フォロー漏れ防止まで一元的に実現できます。
初めてのDXでも導入しやすく、中小企業でも段階的に定着できる点が強みです。
④現場を巻き込むコミュニケーション
DXの導入がうまくいかない最大の要因の一つが、「現場が納得していないまま導入が進むこと」です。ツールの選定や業務プロセスの見直しも、現場の声を聞かずに決めてしまうと、実態と合わずに反発を招きます。
そのため、初期段階から現場を巻き込み、「なぜやるのか」「どう変わるのか」を共有することが欠かせません。
また、「導入して終わり」ではなく、運用フェーズでの声も拾いながら継続的に改善する姿勢が信頼感につながり、定着を後押しします。
⑤定着させるための教育と評価制度
DXを導入しても、それが現場で使われなければ意味がありません。日々の業務の中に自然に組み込まれる状態=定着を目指すには、「教育」と「評価」の仕組み」が重要です。
たとえば、新しいツールの使い方を動画で共有したり、操作に慣れるまでの期間をサポートする体制を整えることで、不安を軽減できます。
また、ツールの活用度や改善提案などを評価項目に入れることで、「DX推進が会社にとって大切な活動である」というメッセージを示すことができます。
よくある社内DXの失敗と対策
「トップダウンだけ」で現場が動かない
よくある失敗の一つが、経営層の指示だけでDXを進めようとして、現場の協力を得られないケースです。現場の課題や業務フローを把握しないまま進行すると、「また意味のない施策が始まった」と受け取られ、実際には運用されないまま形骸化してしまいます。
このような事態を避けるには、現場のキーマンを巻き込んだ“ボトムアップ型”の導入設計が不可欠です。現場の意見を反映させ、「自分たちの業務が便利になる」実感を持たせることが、継続と成果につながります。
目的が曖昧で続かない
「DXをやらなければいけないらしい」といった曖昧な目的で始めてしまうと、途中で方向性がぶれてしまい、続かなくなるという問題もよく見られます。特に、成果がすぐに見えづらい業務改善では、目的の不明確さが現場のモチベーション低下につながります。
対策としては、「何のためにDXをするのか」「何を変えたいのか」を明文化することが大切です。たとえば「営業の進捗が見えづらい課題を改善するためにDXを導入する」など、具体的な課題とゴールを設定することで、軸のぶれを防ぐことができます。
ツール導入が目的化してしまう
もう一つのよくある失敗が、DX=ツール導入と捉えてしまい、システムを入れることがゴールになってしまうパターンです。高機能なツールを導入したものの、使い方が分からない、現場に合っていない、といった理由でまったく活用されない事例も多くあります。
本来、ツールは課題解決の手段であって目的ではありません。導入前には、「このツールで何を解決したいのか」「どの業務がどう変わるのか」を明確にし、“業務起点”でツールを選定・活用する視点が求められます。
中小企業の成功事例:段階的に変革したDX実践例
事例①:紙とExcelを脱却し、商談管理を効率化(クラウドサービス サスケ)
都内にある従業員30名規模の専門商社では、これまで紙の営業日報とExcelで商談情報を管理していました。しかし、「誰がどの顧客にどんな提案をしているのか」が分かりづらく、営業担当者同士の引き継ぎやフォローが属人的になっていることが大きな課題でした。
そこで導入されたのが、クラウドサービス サスケです。サスケを活用することで、商談履歴・顧客情報・対応メモをすべて一元管理。営業メンバーが日々の活動を入力するだけで、マネージャーも進捗をリアルタイムで把握できるようになりました。
また、成功した提案内容や顧客の反応も蓄積されるため、過去のナレッジを参考にした提案が可能になり、営業チーム全体の提案力が底上げされました。現場の負担を抑えつつ、「使えば使うほどラクになる」実感が得られたことで、自然と定着した事例です。
事例②:属人化していた営業ノウハウをチームで共有(ナレッジ活用)
地方でサービス業を営む企業では、営業部門のベテラン社員が持つノウハウが属人化し、他のメンバーに伝わっていないという課題を抱えていました。新人は「どんな順序で顧客にアプローチすればよいか分からない」と悩み、結果として提案内容のバラつきや失注が多発していたのです。
そこで取り組んだのが、ナレッジ共有の仕組み作りです。過去の商談内容や顧客からの質問、成功したクロージングのパターンなどを、営業メンバーがツール上に簡単に記録・検索できる環境を整備。特別な研修をしなくても、他メンバーの提案内容を“見て学べる”体制が実現しました。
結果として、新人の成長スピードが大幅に向上し、提案精度も高まりました。属人化の解消だけでなく、“個人の成果”が“組織の成果”に転換された成功事例です。
【Q&A】社内DXに関するよくある質問
Q:DX担当に選ばれました。まず何から始めるべき?
まずは、「なぜDXが必要なのか」「どんな業務に課題があるのか」を整理しましょう。
いきなりツールの比較や導入検討を始めるのではなく、現場の声を聞きながら、紙やExcelで非効率な業務を洗い出すことが重要です。
そのうえで、小さな業務改善から着手し、成果を実感しながら広げていくことが成功の近道です。
Q:ITが苦手な現場でも進められますか?
はい、むしろITに不慣れな現場こそ、段階的に取り組むDXが効果を発揮します。
たとえば、「紙の書類をGoogleフォームにする」「電話報告をチャットに置き換える」など、小さな“変化”からスタートすることが可能です。
また、直感的に使えるツールや、操作研修が用意されたサービスを選ぶことで、現場の抵抗感を減らすこともできます。
Q:効果はどのくらいで見える?
業務内容や導入範囲にもよりますが、部分的なDXであれば、数週間〜1か月で効果を実感できるケースもあります。
たとえば、営業日報のデジタル化によって集計作業がなくなり、管理者の作業時間が週5時間削減された事例もあります。
ただし、全社的なDXとなると、効果が見えるまでに3か月〜半年以上かかることもあるため、段階的に成果を評価しながら進めることが大切です。
まとめ:社内DXの第一歩は“完璧を目指さない”こと
社内DXを進める際に最も大切なのは、すべてを一度に変えようとせず、小さな成功体験を積み重ねることです。
初めから全社導入を目指すのではなく、一部の業務や部署からデジタル化を始めて拡張していくことで、現場の負荷を抑えつつ変化を浸透させられます。
DX の目的は「ツールを導入すること」ではなく、「現場が使い続け、業務が改善されること」。
だからこそ、まずは“できる範囲”の改革から始め、徐々に全体へ広げていく方針が、社内DXを成功に導く鍵となります。
社内DXを“現場で使われて成果を生む基盤”にしたいなら、サスケ
ただツールを導入しても、現場に使われなければDXは形骸化してしまいます。
クラウドサービス サスケ は、社内DXを“現場目線で使われる形”に落とし込む設計と支援を持ったツールです。
- 顧客・リード・商談情報を 一元管理 し、ツール分断・情報の分断を防止
- AI による優先度提案・スコアリング で判断を補助し、手間を削減
- メール配信・ナーチャリング・タスク管理といった機能を統合し、業務の流れをスムーズに
- スモールスタートに対応した導入設計 で、まずは一部業務から導入できる
- 操作性を重視した UI/UX 設計で、IT 苦手な現場でも扱いやすく
- 活動ログや KPI を 可視化するダッシュボード で、成果をチームみんなで共有
ツールはあくまで手段。DX を“使われない投資”にしないためには、現場が自然に使える状態をつくることが不可欠です。
社内DXを成果につなげたいなら、まずはサスケでその第一歩を踏み出してみてください。
無料デモ・資料請求で、使いやすさと効果をぜひご確認ください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。