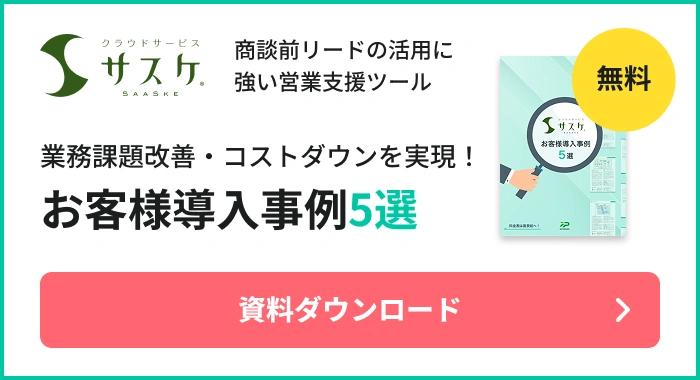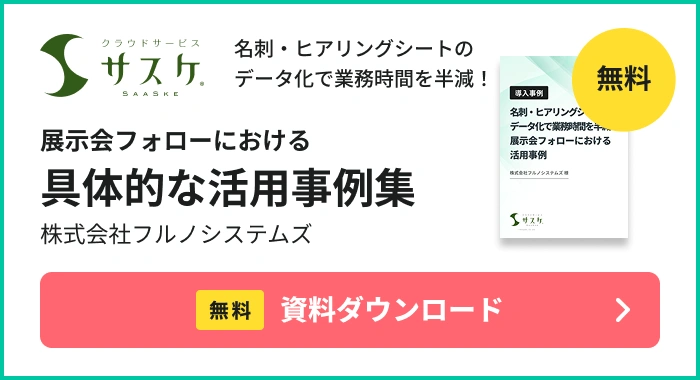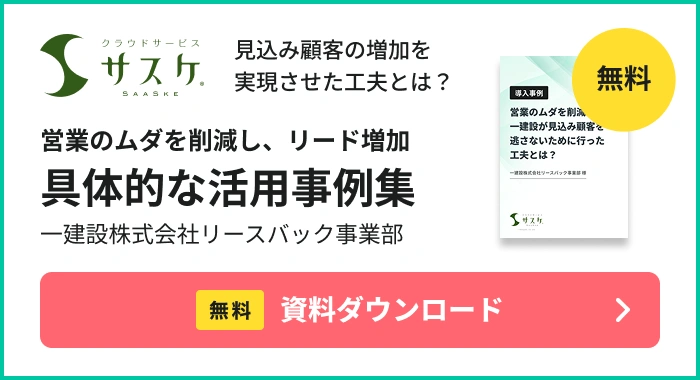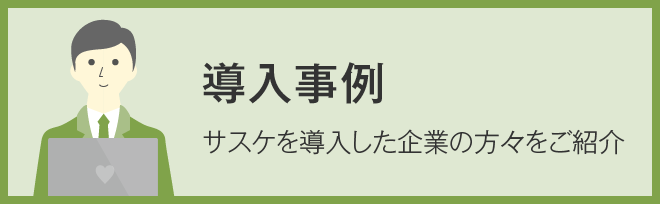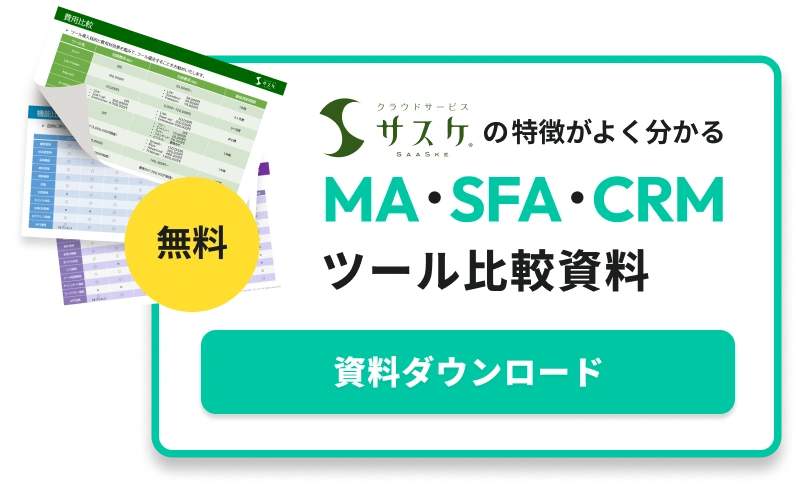AIの進化により、営業活動にも新たな武器が登場しています。その代表例が「ChatGPTを活用した営業スクリプトの自動生成」です。
「属人化した営業トークをどうにかしたい」「新人が成果を出せる仕組みを作りたい」──そんな課題を抱える営業マネージャーにとって、ChatGPTはまさに心強い相棒になり得ます。
本記事では、現場で実践できるスクリプト作成の手順やプロンプトの工夫、業種別テンプレートまで詳しく解説。営業の質と成果を底上げしたい方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
ChatGPTで営業スクリプトを作成するべき理由
属人化した営業トークの課題
営業チームでは、成果が出る人・出ない人の差が広がりやすい傾向があります。その原因の多くは、営業トークが属人化していることにあります。
ベテランの話し方や切り返し術は暗黙知になりやすく、他のメンバーに伝承されにくいのが実情です。結果として、新人や中堅社員が安定して成果を出しづらい状態が続いてしまいます。
スクリプトがあることで得られる3つの効果
1. トークの質の均一化
誰が対応しても一定レベルの提案やヒアリングができるようになります。
2. 新人育成の効率化
「とりあえず横について学ぶ」から脱却し、再現性ある育成が可能になります。
3. アポ獲得率や受注率の改善
事前に成果の出るパターンを繰り返し使えるため、トーク全体の成功率が高まります。
ChatGPTで営業スクリプトを作成する基本ステップ
ステップ①:ターゲットと目的の明確化
ChatGPTに何を作ってもらうかは、「誰に、何を、どう伝えるか」を事前に整理することから始まります。
たとえば「IT部門の課長に向けて、業務効率化ツールを紹介する初回架電用トーク」というように、ターゲットとゴールを具体的に定めることで、生成されるスクリプトの質が大きく変わります。
目的が曖昧なままだと、曖昧な文章しか出てこない──これはChatGPT活用の大原則です。
ステップ②:プロンプトの作成と出力の調整
ターゲットが決まったら、ChatGPTへの指示文(プロンプト)を作成します。
プロンプトでは以下のような要素を盛り込むと、より実用的なスクリプトが得られます。
- ターゲットの属性(例:中小企業の情シス担当)
- 想定シーン(例:初回架電、ヒアリングフェーズ)
- トークの長さ(例:1分以内)
- 営業側のスタンス(例:悩みを聞き出す、軽いジャブ程度の紹介)
また、出力された内容をそのまま使うのではなく、トーン・言い回し・用語の専門性などを何度か調整することが重要です。少しずつ会話しながらブラッシュアップしていくことで、より自社に合った営業文が完成します。
また、ChatGPTの出力は一度に多くの情報を盛り込みすぎると、「一文が長くなる」「要点がぼやける」といった傾向があります。特に初心者の方は、以下のような工夫をすると出力品質が向上します。
- 要素を分けて依頼する:「まず冒頭トーク、次に商品紹介」と段階的に生成依頼する
- トーンや語尾の指示を追加する:「丁寧語・親しみやすさ・語尾を統一」など明示する
- 長さ制限を明記する:「60秒以内」「300文字程度」など、文字数や時間の目安を加える
これらの調整を重ねながら、ChatGPTと“対話する感覚”でスクリプトを練っていくことで、自社のトーンや営業スタイルに最適化されたスクリプトが出来上がっていきます。
ステップ③:現場のフィードバックを反映してブラッシュアップ
ChatGPTが生成するスクリプトはあくまで「たたき台」です。
実際の商談や架電で使った後は、現場の反応を元に修正を加えることで、使えるスクリプトに昇華していきます。
ここでは、以下のような観点で評価・改善していきましょう。
- 話の流れは自然だったか
- 相手の関心を引くフレーズがあったか
- 話が長すぎたり、要点が伝わらなかった箇所はなかったか
属人化の解消という観点では、修正されたスクリプトをチーム全体で共有する文化をつくることも大切です。
現場で使える!営業スクリプトの具体例(業種別・目的別)
初回架電用(例:IT部門向け/製造業向け)
ターゲット:中堅製造業のIT担当者
目的:話を聞いてもらう時間(約1分)を確保し、概要紹介のきっかけをつくること
「お忙しいところ恐れ入ります。〇〇株式会社の佐藤と申します。突然のご連絡で恐縮ですが、御社のような製造業向けに、現場業務をペーパーレス化・自動化するクラウドサービスをご案内しております。短時間で概要だけご説明できればと思いご連絡しましたが、今1分ほどお時間よろしいでしょうか?」
→ 冒頭の目的が明確になることで、トーク設計の意図が理解しやすくなります。
商談フォロー用(例:価格に迷っている相手への対応)
目的:再提案や歩み寄りの余地を提示し、失注を防ぐ
「先日のご提案内容、ご確認ありがとうございました。お見積り金額についてご検討中とのことですが、もしご予算の目安や社内での承認条件などがあれば、そちらに沿ったご提案やプラン変更も可能です。お気軽にご相談ください。」
このように、反応が鈍ってきたフェーズで次の一手を打つトークもChatGPTで量産可能です。
クロージング用(例:稟議突破・社内説得)
目的:社内稟議をスムーズに通す材料を提供し、意思決定を後押しする
「ご検討ありがとうございます。もし社内でご共有される場合には、費用対効果や実績資料などもご提供可能ですので、稟議資料作成にお役立てください。導入後の活用イメージもまとめております。」
BtoBでは「社内で決済が下りるか」が最大の壁になることも多いため、その突破を意識したトークスクリプトを作るのも重要です。
ChatGPTプロンプト例|そのまま使えるテンプレート集
ターゲット業界ごとのプロンプト例
ChatGPTで営業スクリプトを生成する際は、「誰に・何を・どう伝えるか」をできるだけ具体的にプロンプトに書くことが重要です。以下はそのまま使える実践的なプロンプト例です。
例1:IT企業向け 初回アプローチ(架電用)
「あなたは営業担当者です。中小企業のIT部門の課長に、業務効率化のSaaSサービスを初めて紹介する電話の冒頭トークを考えてください。60秒以内で、相手の課題に共感しながらヒアリングにつなげる構成にしてください。」
例2:製造業向け 商談フォロー用メール
「先日オンライン商談を実施した企業のIT担当者宛に、製造現場の業務改善ツールのフォローアップメールを作成してください。価格面を懸念している相手に、導入メリットを定量的に伝えてください。」
例3:決裁者向け クロージングトーク
「見積もり提示済みの案件で、役員決裁待ちの顧客に電話をかける想定です。稟議を通すために必要な支援(資料提供・導入事例など)を申し出るクロージング用トークを考えてください。」
こうしたプロンプトを蓄積・展開することで、組織全体の営業力を底上げすることができます。
よくある失敗と改善ポイント
ChatGPTを使ったスクリプト作成でよくある失敗例は、次の3つです。
1. プロンプトが抽象的すぎる
「営業トーク作ってください」では汎用的すぎて使えません。誰に・どんな場面で・何を目的に話すかを明示しましょう。
2. 出力されたままの文章をそのまま使ってしまう
ChatGPTの回答はあくまで“素材”です。語尾・トーン・長さを自社のスタイルに合わせて調整しましょう。
3. フィードバックを得ずに1人で完結させる
実際の使用後に「使いやすかったか」「相手の反応はどうだったか」を現場から収集→再修正することで、実戦的なスクリプトに進化します。
よくある質問(FAQ)
Q. ChatGPTの営業スクリプトはどこまで信頼できますか?
あくまで“下書き”として使う前提であれば、実務でも十分活用可能です。
特に、初回架電やフォローアップなど「ある程度パターン化できる場面」では高い再現性があります。一方で、相手の反応に応じた即時対応には人間の判断が必要です。
Q. 営業経験が浅くても使いこなせますか?
はい。むしろ新人の方がChatGPTの恩恵を受けやすいです。
経験が少なくても、トークの型や切り返し例を事前に準備できるため、現場での自信にもつながります。ベテランが作成したプロンプトを共有する運用も有効です。
Q. セキュリティ上の不安はありませんか?
ChatGPTの利用においては、個人情報や機密情報を入力しないことが大前提です。
営業スクリプトのような汎用的・公開前提の情報であれば問題ありませんが、社名・担当者名・具体的な商談情報などは入力しない運用ルールを設けると安全です。
営業効率をさらに高めるには?クラウドサービスとの連携がカギ
ChatGPTで営業スクリプトを自動生成すること自体は強力な武器ですが、それをチームで運用・改善していく仕組みがなければ宝の持ち腐れになってしまいます。
最終的に重要なのは、スクリプトの管理・振り返り・共有を含めて一元化できる仕組みを持つこと。
そのためには、ChatGPTとの連携が可能なクラウド営業支援ツールを導入し、現場で使われ、改善される循環を設計することが成功への分かれ道です。
ChatGPTで作ったスクリプトを“育てながら成果につなげる基盤”にしたいなら、サスケ
ChatGPTでスクリプトを作るところで止めず、それを継続的に使われ、改善され、チームで資産化する設計が不可欠です。
クラウドサービス サスケ は、スクリプト生成と営業支援の連携を重視したツールとして次のような強みを持っています。
- 生成したスクリプトの保存・共有機能により、チーム全体でトークを可視化
- 商談後の反応ログ・振り返りを記録し、スクリプトを改善する材料として蓄積
- 成果の出たトークをナレッジ化し、新人育成や横展開につなげる仕組み
- 一元管理された対応履歴とスクリプト活用履歴により、改善効率を向上
- 操作性を重視したUX設計と連携性で、ChatGPTとクラウドツールをスムーズにつなぐ
ChatGPTで作ったスクリプトを 「使われる資産」 に変えたいなら、サスケを導入候補にぜひ加えてみてください。
無料デモ・資料請求で、その連携力と定着力をご体感ください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。









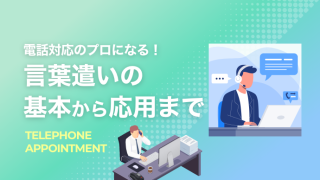


-1-640x360.jpg)