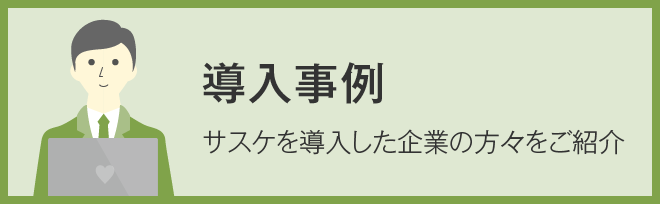「情報システム部門の役割とは?」と調べる背景には、多くの場合、従来の“ITサポート担当”という枠を超え、経営に貢献する存在になることを求められている状況があります。
社内からは日々のヘルプデスク業務やシステム管理が期待されつつも、経営層からは「もっと戦略的に動け」とプレッシャーを受けている──そんな悩みを持つ情報システム部門の責任者は少なくありません。
本記事では、情シスの役割を「守り」と「攻め」で整理し、他社事例や課題・解決策を交えながら、これからの部門像を明確にしていきます。
Contents
なぜ今「情報システム部門の役割」が注目されているのか?
単なるITサポートでは限界がある
これまで多くの企業で情報システム部門は、PCセットアップやアカウント管理などの“社内の便利屋”的な存在として認識されがちでした。
しかし、クラウドサービスの普及・セキュリティリスクの増大・DX推進の流れによって、単純なITサポートだけでは企業競争力を維持できません。
「なぜ自社に情シスが必要か?」を明確化することが、今や企業経営に直結する課題になっています。
経営層が求める「戦略的な情シス」とは
経営層が期待するのは、単なる保守運用ではなく、事業に寄与する情報活用のハブとしての役割です。
たとえば、データ分析による意思決定支援、新規事業を支えるシステム導入、全社の働き方を変えるツール展開など。
つまり情シスは、「守り」=安定稼働の維持と「攻め」=ビジネス成長への貢献という二軸での存在感が求められているのです。
情報システム部門の基本的な役割とは?
守りの役割:インフラ・セキュリティ・ヘルプデスク
守りの役割は、企業活動の安定を支える基盤です。具体的には以下のような業務が中心です。
- ネットワーク・サーバの維持管理
- 情報セキュリティ対策(不正アクセス・ウイルス・内部不正の防止)
- 社員からの問い合わせ対応(ヘルプデスク)
これらは「できて当たり前」と思われがちですが、実際には企業の信頼性を左右する重要な業務です。
攻めの役割:DX推進・データ活用支援
一方で、近年注目されているのが「攻め」の役割です。
- クラウドやSaaSの導入・定着を通じた業務効率化
- データ活用による意思決定支援
- 現場部門と連携した業務プロセス改善
情シスが主体的にこうした取り組みをリードすることで、企業は単なるコスト削減だけでなく、売上向上や新規ビジネスの創出といった成果を期待できます。
他社事例から学ぶ!情報システム部門の進化
製造業の事例:生産データの分析によるコスト削減
ある中堅製造業では、情報システム部門が中心となり、生産設備から収集したデータを分析。
その結果、稼働率や不良率の可視化に成功し、無駄なコストを年間数千万円規模で削減できました。
従来は工場現場の経験や勘に頼っていた改善活動を、データドリブンで進められるようになった点が大きな成果です。
小売業の事例:顧客データ活用で売上向上
大手小売企業では、POSシステムやECサイトから集めたデータを情報システム部門が統合し、マーケティング部門へ提供しました。
これにより、購買傾向に基づくキャンペーン設計や在庫最適化が可能になり、売上が前年比10%以上伸長。
情シスが“裏方”ではなく、ビジネス部門の成果に直結する役割を果たした好例です。
サービス業の事例:クラウド導入による業務効率化
中小規模のサービス業では、情報システム部門がクラウドサービスを導入。
紙ベースで行っていた予約管理や顧客対応をデジタル化した結果、現場スタッフの残業時間が30%削減されました。
クラウド活用により、限られた人員でもスムーズに運営できる仕組みを構築できたのです。
情報システム部門が直面する課題と解決策
人員不足・属人化
多くの企業では、情報システム部門の人数はごく少数。
そのため特定の担当者に知識やノウハウが偏り、「その人がいないと回らない」状態になりがちです。
属人化は業務リスクを高めるだけでなく、担当者の負担増による離職にもつながります。
「コストセンター」と見られるリスク
情シスは直接的に売上を生む部門ではないため、経営層や他部署から「コストばかりかかる部門」と見られることも少なくありません。
この評価が続くと、予算削減や人員削減の対象となり、さらに役割を果たせなくなる悪循環に陥ります。
改善に向けた具体策
アウトソースの活用
ヘルプデスクやシステム保守など定型的な業務は、外部ベンダーに委託することで負担を軽減できます。
社内の限られた人材は、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
SaaS導入による効率化
クラウドサービスやSaaSを導入することで、日々の運用工数を削減できます。
たとえばクラウドサービス サスケを使えば、顧客情報や営業活動を一元管理でき、属人化を防ぎながら効率的にデータを活用できます。
社内教育・ナレッジ共有の仕組み化
属人化を防ぐには、マニュアル作成やナレッジ共有の仕組み化が欠かせません。
教育体制を整備し、誰でも一定レベルの業務をこなせる環境をつくることで、部門全体の安定性が向上します。
戦略的な情報システム部門になるためのステップ
役割マップを作成して社内に共有する
まずは、自社における情報システム部門の役割を「守り」と「攻め」に分け、役割マップとして整理しましょう。
「インフラ管理」「セキュリティ」「業務改善」「データ活用」といった領域を明確化することで、経営層や他部門に情シスの存在価値を伝えやすくなります。
業務の可視化と改善サイクル
次に重要なのは、日々の業務を可視化することです。
タスクやプロジェクトを一覧化し、PDCAサイクルを回せる仕組みをつくれば、部門として継続的に改善できます。
これにより「何をやっているか分からない」という不満を払拭し、社内からの理解を得やすくなります。
ツール活用による効率化(例:クラウドサービス サスケ)
業務効率化の実現には、適切なツールの導入が欠かせません。
例えばクラウドサービス サスケを利用すれば、営業活動や顧客データを一元管理でき、情報システム部門が全社の業務改善を支援しやすくなります。
ツール活用は、情シスを「単なるIT担当」から「全社を支える戦略的パートナー」へと進化させる武器になります。
経営層への提案力を強化する
最後に、経営層への説明力・提案力を磨くことが大切です。
IT専門用語をそのまま使うのではなく、「どのように売上やコスト削減につながるのか」という経営目線で語れることが、情シスの評価を大きく変えます。
数字や事例を交えたプレゼン資料を準備し、定期的に経営層へ報告する仕組みを持ちましょう。
よくある質問(FAQ)
情シスと社内SEの違いは?
一般的に「社内SE」は情報システム部門の一員を指すことが多く、立場の違いよりも業務範囲の呼び方の違いです。
ただし社内SEは技術寄りの意味合いが強く、情シスは企画や運用管理も含む幅広い役割を担うケースが多いです。
情報システム部門の人数はどれくらい必要?
企業規模や業務範囲によりますが、従業員100〜200人規模で3〜5人程度が目安とされています。
ただしクラウドやアウトソースを活用すれば、少人数でも十分に運営できます。
アウトソースすべき業務は?
ヘルプデスクや機器設定など、定型化できる業務はアウトソースに適しています。
一方で、DX推進やデータ活用などの戦略領域は、社内の情シスが主体的に担うべきです。
まとめ:情シスは「守り」と「攻め」で会社を支える存在へ
情報システム部門は、もはや単なる“ITサポート”にとどまらず、インフラやセキュリティなどの「守り」と、DX推進やデータ活用などの「攻め」の両面で企業を支える存在が求められています。
ただし、その役割を果たすには、どちらか一方に偏るのではなく、日常業務の安定運用を担保しながら、戦略的な仕組みを現場に根づかせる両立型のアプローチが不可欠です。
情シスを“戦略的ハブ”に変えたいなら、サスケ
情シス部門を「守りの裏方」から “経営と現場をつなぐ戦略的ハブ” に変えたいなら、ただツールを導入するだけでは不十分です。
クラウドサービス サスケ は、情シスが本来担うべき両軸を支え、現場に定着させるための設計とサポートを備えています。
- 顧客・案件・対応履歴・リード情報を 一元管理 し、“データの断片化”を防ぐ
- AI によるスコアリングや優先度提案 を通じて、営業判断の属人性を削減
- メール配信・ナーチャリング・タスク管理などを統合し、業務の連携性を高める
- UI/UX を重視した設計で、ITに詳しくない現場でも自然に使える
- スモールスタート対応 により、まずは一部機能から段階導入できる
- 活動ログ・KPI 可視化ダッシュボードで 成果の見える化 を支援
守りも攻めも、両方を支える根幹をつくりたいなら、サスケを導入候補としてご検討ください。
無料デモ・資料請求で、現場で使える戦略的情シス体制の実感を得てみてください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
最新の投稿
 営業2025年10月16日【2025年版】AI自動化とは?導入メリット・失敗しない進め方・中小企業事例とおすすめツール
営業2025年10月16日【2025年版】AI自動化とは?導入メリット・失敗しない進め方・中小企業事例とおすすめツール 営業2025年10月15日CRM運用を成功させる設計と定着ノウハウ|サスケ/カゲマル活用も含めた実践ガイド
営業2025年10月15日CRM運用を成功させる設計と定着ノウハウ|サスケ/カゲマル活用も含めた実践ガイド 営業2025年10月15日【2025年版】CRMの主な機能とは?営業効率化に役立つ機能一覧と選び方
営業2025年10月15日【2025年版】CRMの主な機能とは?営業効率化に役立つ機能一覧と選び方 サスケの使い方2025年10月15日【活用術】リード管理で成果を上げるサスケのおすすめ機能5選
サスケの使い方2025年10月15日【活用術】リード管理で成果を上げるサスケのおすすめ機能5選