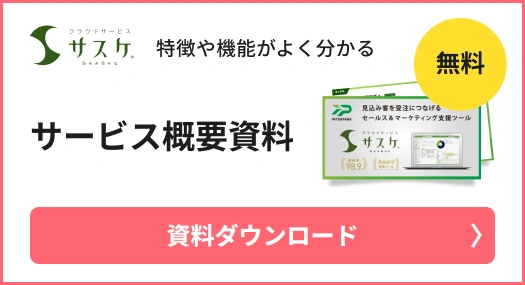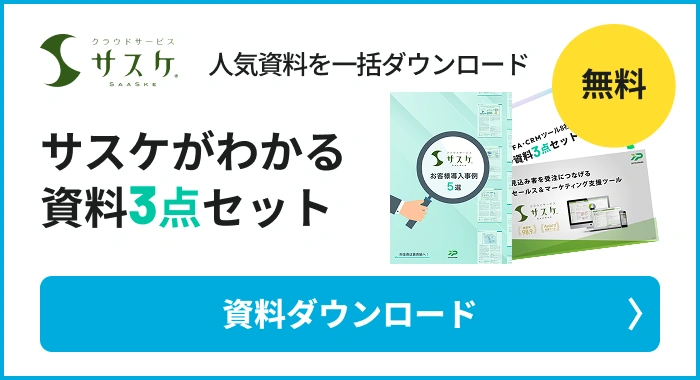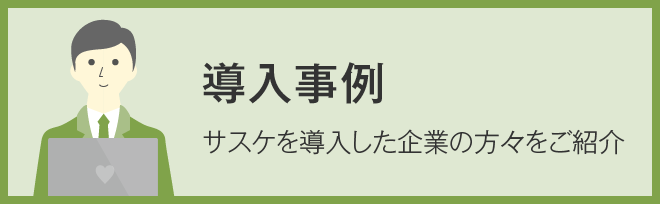業務の属人化や新人教育に課題を感じ、「社内マニュアルを作成したい」と思っても、何から始めればよいかわからないという声は多く聞かれます。特に中小企業では、時間も人手も限られており、誰もが手探りで進めることになりがちです。
この記事では、初めてマニュアル作成に取り組む方でも実践しやすい方法を、ステップごとにわかりやすく解説します。テンプレートの型やツール選び、運用のポイントまでしっかりカバーしているので、読み終える頃には「これならできそう」と思えるはずです。
なぜ今、社内マニュアルが必要なのか
業務の属人化がもたらすリスク
特定の社員しか内容を把握していない業務があると、その人が不在になるだけで業務が止まる、品質が落ちる、顧客対応が遅れるといったリスクが発生します。さらに、その人が退職した場合にはノウハウがごっそり抜け落ちることも。マニュアル化されていない業務は、企業にとって“見えない爆弾”とも言える存在です。
新人教育の効率化と業務平準化
「毎回口頭で教える」「人によって説明が違う」といった非効率な教育体制では、教える側の負担も大きく、習得側の理解度にも差が出てしまいます。マニュアルがあれば、誰が指導しても一定レベルの教育が可能となり、新人も自ら復習・確認ができます。また、現場での「これってどうするんでしたっけ?」という質問を減らす効果も期待できます。
社内マニュアル作成の5ステップ
①目的と対象業務の明確化
いきなり書き始めるのではなく、まずは「何のために、どの業務について書くのか」を明確にしましょう。
例:
・新人がスムーズに業務を始められるようにする
・バックオフィスの業務フローを標準化する
・営業活動の属人化を減らす
対象業務の選定に迷ったら、属人化が強く、かつ繰り返し発生している業務から始めるのがおすすめです。
②構成のテンプレートを決める
マニュアルには「型」があると、書く側も読む側も迷いません。以下のようなシンプルな構成をベースにすると良いでしょう。
目的/手順/注意点/補足情報が基本
- 目的:この業務がなぜ存在するのか
- 手順:時系列で具体的に
- 注意点:間違えやすいポイントや判断の分岐
- 補足情報:使用ツールのリンクやQ&A
すべての業務にこの枠組みが必要というわけではありませんが、読み手にとっての「迷わない設計」を意識することが大切です。
③現場ヒアリングと情報収集
実際にその業務を行っている人からの現場ヒアリングは不可欠です。
「とりあえず書いてみたが、実情と違って使えない」というマニュアルは少なくありません。必ず現場の声を拾い、現在のやり方・例外対応・困っている点なども含めて把握するようにしましょう。
メモの段階では箇条書きでもOKです。のちの整理に役立つよう、録音・録画・画面キャプチャなどを活用するのも有効です。
④わかりやすく書くためのコツ
曖昧な表現を避ける/画像や動画も活用する
「適宜対応」「なるべく早く」「しっかり確認」などの曖昧な表現は避けましょう。誰が見ても同じ行動が取れるよう、具体的な数値や判断基準、操作手順を明記することが重要です。
また、画像や動画の挿入もおすすめです。特にツール操作や画面の説明などは、文字より視覚情報の方が伝わりやすく、定着もしやすくなります。
たとえば:
- スクリーンショットに赤枠や吹き出しで補足
- 簡単な操作動画をスマホで録画して貼り付け
など、凝りすぎなくても伝わる工夫がポイントです。
⑤運用と定着のための仕組みづくり
定期レビュー/更新担当の設定/フィードバック受付窓口
マニュアルは一度作って終わりではなく、使われ続けてこそ意味があります。そのために、以下の仕組みを整えておきましょう。
- 定期レビューのタイミング(例:半年ごと、年度末)
- 更新担当者の明確化(例:業務の実行責任者)
- 現場からのフィードバックを集める仕組み(Googleフォームなど)
さらに、更新履歴を残す・最終更新日を明記することで、閲覧者の信頼性や安心感も高まります。
おすすめのマニュアル作成・管理ツール
Googleドキュメント|無料かつ社内共有に強い
社内マニュアル作成の第一歩として、多くの企業が活用しているのがGoogleドキュメントです。
リアルタイムでの共同編集や閲覧権限の柔軟な設定が可能で、テンプレート化もしやすいのが特徴です。
クラウド上で保存されるため、場所を問わずアクセス・編集できる点も中小企業にはメリットが大きいです。
Notion|柔軟な構造で育てるマニュアルに最適
Notionは、ページ構造が柔軟でリンク管理もしやすく、ナレッジベースとしても使える点が魅力です。
階層構造やタグ管理がしやすいため、業務が複雑・多岐にわたる部署でも整理しやすいです。社内Wiki的な使い方をしたい場合には特におすすめです。
サスケ|営業部門向けの業務共有・ナレッジ蓄積にも強み
「クラウドサービス サスケ」は、営業活動における情報共有やプロセスの可視化、リード管理に強みを持つSFAツールです。
マニュアルそのものを格納するというよりは、営業現場での業務フローや活動状況を「見える化」し、ナレッジを組織内で活用するための基盤として活用されています。
たとえば:
- 営業プロセスごとに対応すべきアクションの一元管理
- 過去の案件履歴から成功パターンを把握・共有
- リード情報や接点履歴の可視化による属人化の防止
マニュアルの整備と並行して、営業ナレッジの蓄積・展開を仕組み化したい企業にとって、非常に有効なツールです。
よくある質問(FAQ)
マニュアルはPDF形式で配ってもいいの?
PDFでの配布も可能ですが、更新性と検索性の観点からは非推奨です。
PDFは「印刷して使う」には便利ですが、業務が変わった際の更新が面倒で、最新版がどれかわかりにくくなるケースも。
そのため、GoogleドキュメントやNotionなどクラウド上で更新・共有できる形式をベースにし、必要に応じてPDF出力するスタイルが実用的です。
最初に整備すべき業務マニュアルは?
頻度が高く、属人化している業務から手をつけるのが効果的です。
たとえば:
- 新人教育に毎回時間がかかる業務(例:日報の書き方、ツールの使い方)
- 問い合わせ対応が多い業務(例:請求書発行、備品申請)
- 休みのたびに「代わりにできる人がいない」となる業務
現場の困りごとをヒアリングしながら、影響範囲が広い業務から優先的に整備しましょう。
マニュアル作成にかける時間や人員はどれくらい?
対象業務のボリュームによりますが、1業務あたり2〜3時間程度が目安です(情報整理・執筆・レビュー含む)。
一度にすべて作るのではなく、月に数本ずつ継続して作成・整備していくスタイルが現実的です。
人員については、
- 作成担当:業務に一番詳しい人(現場)
- 監修者:内容のチェックをする責任者
- 管理担当:更新・フォーマット整備
といった分担体制を作っておくと負荷が分散され、運用が続きやすくなります。
まとめ|最初の一歩を小さく始め、継続できる仕組みを
社内マニュアルは、「完璧を目指してから始める」ものではありません。まずは1つの業務から、小さく始めることが大切です。
属人化を解消し、新人教育の負担を減らし、現場の混乱を防ぐ——そのための第一歩が、わかりやすく使われるマニュアルです。
そして作成後は、運用・更新の仕組みまで整えてこそ「活きたマニュアル」になります。
営業やバックオフィスなど、部門ごとに情報の整理・活用を進めたい場合には、「クラウドサービス サスケ」のようなツールを活用することで、より効率的な運用も可能になります。
次は、貴社に合ったツール選定やテンプレート作成から、実際のマニュアル整備に着手してみてください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。