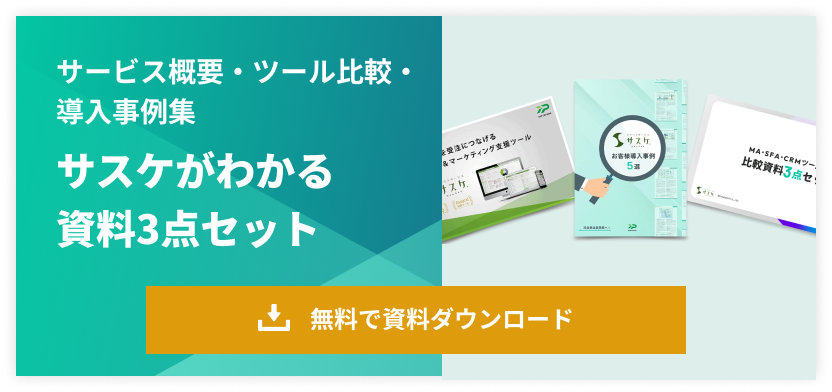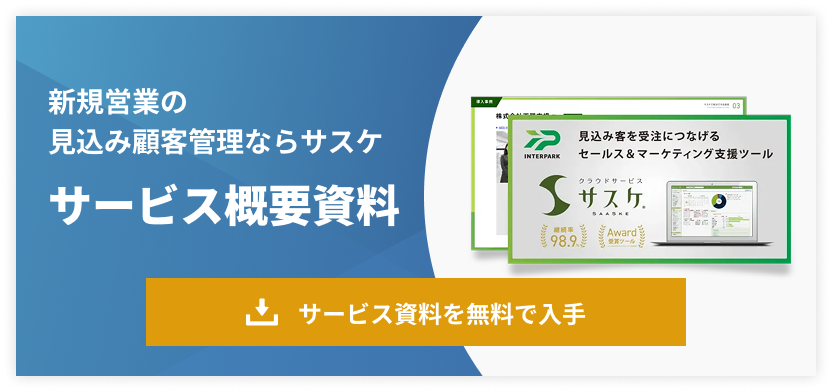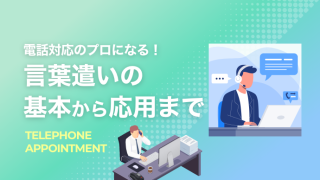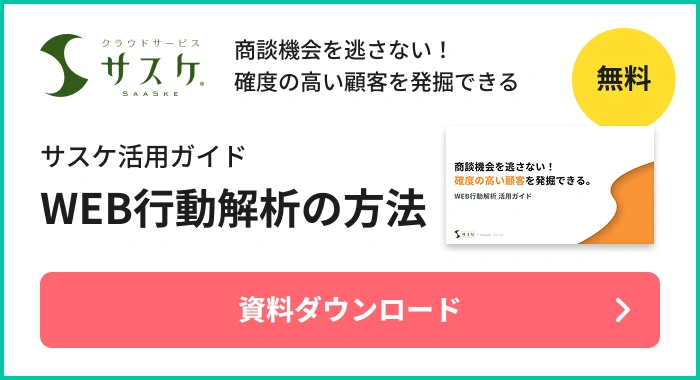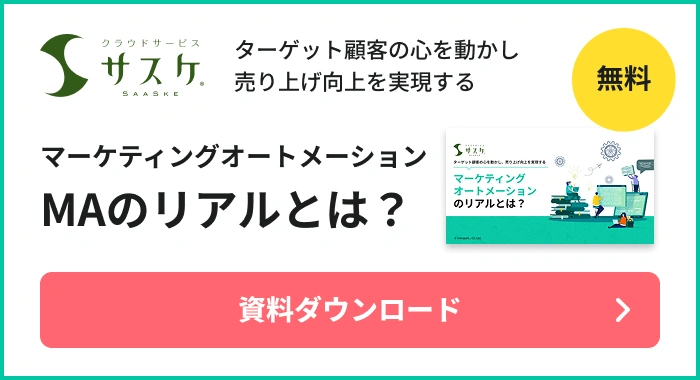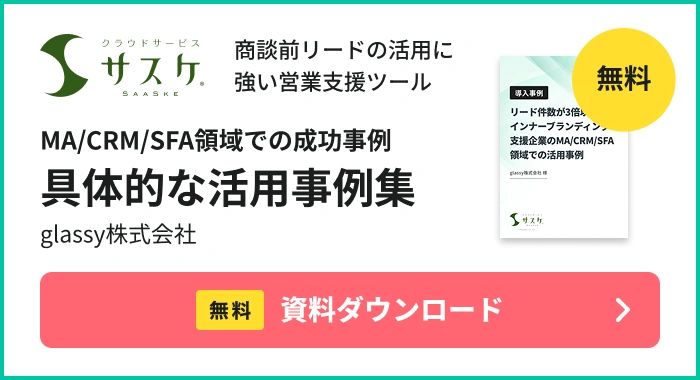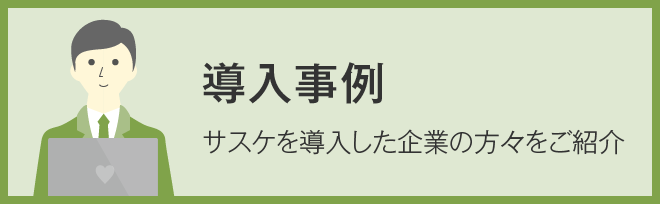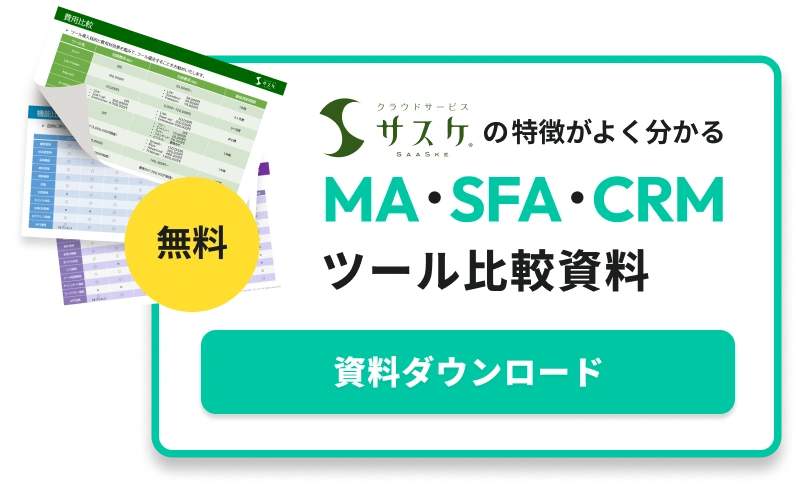営業とマーケティングは、どちらも企業の売上を伸ばすために欠かせない存在です。
しかし現場では「マーケはリードを増やすばかりで質が低い」「営業はせっかくのリードを追わない」といった対立が生まれがちです。その結果、せっかくの施策が成果につながらず、経営層からも厳しい目で見られてしまうケースは少なくありません。
本記事では、営業とマーケが連携して成果を最大化するための具体的な方法を、実際の事例や成功のポイントとともに解説します。
Contents
なぜ営業とマーケの連携が必要なのか?
よくある対立:リード数 vs 商談数
マーケティング部門は「獲得リード数」をKPIにしていることが多く、展示会や広告施策で集めた名刺や問い合わせ数を成果として評価されます。
一方で営業部門は「商談数・受注数」を最重要視します。このKPIのズレが“リードは多いのに商談にならない”という不満を生み、部門間の摩擦につながる典型的な原因です。
属人化と情報分断が生む非効率
営業担当がExcelや個人のメールで顧客管理を行い、マーケはMAツールや広告レポートを使う、といった「バラバラの管理体制」も問題です。
情報が部門ごとに閉じてしまうことで、顧客の一貫したフォローができず、商談機会の取りこぼしや顧客体験の質低下につながります。
営業とマーケが連携するメリット
商談化率・受注率の向上
営業とマーケが共通の指標で協力できれば、「営業が追いやすいリード」を獲得することに集中できます。結果として、商談化率や受注率が上がり、広告や施策のROIも改善します。
顧客体験の一貫性向上
営業とマーケが分断されていると、顧客は「マーケではこう言われたのに、営業担当の提案は違う」といったギャップを感じやすくなります。
しかし連携を強化すれば、顧客接点の最初から最後まで一貫したメッセージを届けることができ、信頼感を高めることが可能です。
営業とマーケ連携の具体的な方法
共通KPIの設計と合意形成
営業とマーケが別々の指標を追っている限り、連携はうまくいきません。
そこで有効なのが「共通KPIの設計」です。たとえば、マーケは「リード数」だけでなく「商談化率」や「SQL(営業が有効と判断したリード)の創出数」までを成果指標に含めることで、営業の目線と一致させることができます。KPIを一緒に作ることで、両部門が同じゴールを見据えられるようになります。
リード定義のすり合わせ(MQL/SQL)
営業とマーケで「良いリード」の定義が異なると、せっかくの顧客データも無駄になります。
そこで必要なのが、MQL(マーケティングが有望と判断したリード)とSQL(営業が商談可能と判断したリード)の明確な定義付けです。例えば「ホワイトペーパーをDLしただけはMQL、フォーム問い合わせをしたらSQL」といった基準を両者で合意しておくことで、スムーズに引き渡しができます。
CRM・SFAを活用した情報共有(例:クラウドサービス サスケ)
営業とマーケの情報分断を防ぐには、Excelやメール共有では限界があります。
CRMやSFAといった仕組みを活用し、顧客情報や進捗をリアルタイムで見える化することが不可欠です。たとえば「クラウドサービス サスケ」のような営業支援ツールを導入すれば、リード獲得から商談・成約まで一気通貫で管理でき、両部門が同じ顧客情報をベースに行動できます。
定例ミーティングとフィードバックの仕組み
システムやKPIを整備しても、人と人のコミュニケーションがなければすぐに形骸化してしまいます。
月次・週次で営業とマーケの合同ミーティングを設け、成果と課題を振り返る場をつくることが重要です。マーケが提供したリードの質を営業がフィードバックする、営業現場の声をマーケ施策に反映させる、といった循環が連携を定着させます。
実際の成功事例
IT企業でのリードナーチャリング改善例
あるIT企業では、マーケ部門が獲得したリードを営業が「冷たい」と判断し、ほとんどフォローしていませんでした。
そこでMAツールとCRMを連携させ、スコアリングに応じてナーチャリング(教育)メールを配信。一定以上のスコアになったリードだけを営業に引き渡すようにしたところ、商談化率が20%以上改善しました。
製造業での営業・マーケ合同施策
製造業のBtoB企業では、展示会での名刺獲得が主なリード獲得施策でしたが、営業がフォローしきれず休眠リードが多発していました。
そこでマーケが展示会後すぐにセミナーやウェビナーを開催し、参加した見込み客を営業に即連携。さらに営業とマーケで合同の施策チームを作り、フォロー手順を標準化した結果、商談数が大幅に増加しました。
営業とマーケ連携が進まない時の対処法
経営層を巻き込む方法
営業とマーケの部門長同士での調整に限界を感じたら、経営層を巻き込むのが有効です。経営層が「売上最大化のために連携が必須」というメッセージを発信すれば、現場も動かざるを得なくなります。トップダウンでの後押しは、組織文化を変えるために欠かせません。
小さなプロジェクトから始める
一方で、いきなり全社改革を狙うと現場が混乱しやすくなります。
おすすめは小さな連携施策からテスト的に始めることです。例えば「展示会で獲得したリードのフォローだけは共通プロセスを導入する」といった限定的な取り組みから始め、成果が出たら範囲を広げていく方が定着しやすいです。
よくある質問(FAQ)
営業とマーケが協力できない一番の原因は?
最大の原因は「目標のズレ」です。マーケはリード数、営業は売上という異なるゴールを追っているため、お互いの活動を評価できなくなります。共通KPIの設定が第一歩となります。
ツール導入と社内文化、どちらを優先すべき?
どちらも大切ですが、まずは文化(意識改革)を整えることが先決です。営業がリードを「マーケの成果物」として軽視していては、どんなツールを導入しても定着しません。共通言語や目標を整えたうえで、CRMやSFAを導入すると効果が最大化します。
まとめ:営業とマーケの連携で組織はもっと強くなる
営業とマーケティングが連携することは、単なる“部門の仲良し作戦”ではありません。
共通KPIの設定・リード定義のすり合わせ・情報共有の仕組みづくりといった要素を整えることで、部門をまたいだ行動が“成果を生む一連の流れ”に変わります。
たとえ小さな施策からでも、今日始められるアプローチを一つでも取り入れれば、リード → 商談 → 受注の流れがスムーズになり、顧客体験の一貫性も向上します。
連携が機能すれば、組織は単なる足し算ではなく、全体として成長するチームになれるのです。
営業 × マーケを“成果につながる一体化”にしたいなら、サスケ
営業とマーケが連携しても、その情報基盤が分断されていては連携効果は限定的です。
クラウドサービス サスケ は、両部門の“共通言語”となる情報プラットフォームとして、連携を成果につなげる基盤を整えます。
- リード~商談~対応履歴を一元管理し、情報断絶を防止
- 共通KPI・リード定義の共有設計支援で部門間の目線を統一
- 営業・マーケ両方で使える UI/UX 設計により、どちらの立場も操作しやすい
- 活動ログ・反応データを 可視化ダッシュボード により両部門で参照可能
- スモールスタート導入 でき、一部施策から段階的に連携を始められる
- 導入支援・定着フォロー体制により、部門間の連携を現場レベルに根づかせる
営業とマーケの垣根をなくし、部門を超えた“成果のシステム”をつくりたいなら、サスケがその第一歩になる選択肢です。
まずは無料デモ・資料請求で、連携基盤としての使いやすさと実行力をご体感ください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。