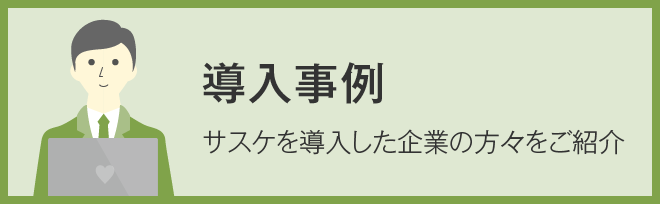中小企業の情シス担当者にとって「DXを進めてほしい」という一言は、抽象的かつ重いプレッシャーを伴います。経営層からの期待はあるものの、具体的な指示がないことも多く、「何から始めればよいのか分からない」という悩みを抱える方は少なくありません。特に情シスが専任ではなく、総務や管理業務と兼任している場合、DX推進に割ける時間やリソースが限られているのが現実です。
本記事では、情シスが現場主導でDXを進めるための実践的なステップと、現場との橋渡しをどう実現するかを中心に解説します。経営層の意図を理解しながら、具体的なアクションにつなげるヒントを紹介していきます。
Contents
情シスがDX推進を求められる背景とは?
DXという言葉だけが一人歩きしていないか?
最近ではニュースや経済紙でも頻繁に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が登場するようになりました。中小企業でも「うちもDXをやらないと遅れてしまう」と焦る声が増えていますが、その多くが“言葉だけが先行”しており、具体的なビジョンやゴールが社内で共有されていないのが実情です。
情シス担当者は、現場業務の知見とシステム管理の両面を持つポジションにあるため、DX推進の役割を任されやすい一方で、「何をもってDXとするのか」「どこから手を付ければいいのか」が不明瞭な状態に置かれがちです。
経営層と現場の“温度差”が情シスに重くのしかかる理由
DX推進においてよくあるのが、経営層は“変革”を期待しているのに、現場は“変化”に消極的というギャップです。この温度差の調整役を担うのが、まさに情シスの役割です。
情シスはシステム面から現場の業務を把握しており、現実的な改善ポイントと、ITの力で変えられる部分を見極める立場にあります。しかし、予算も人も限られた中で、「とにかくDXを」と言われるだけでは、なかなか動き出せません。
こうした背景から、「情シスが主導するDX推進」は、理想と現実のバランスを取りながら、まずは“小さな一歩”を積み上げていくことが重要なのです。
DXの定義と、情シスが担うべき役割を整理する
IT導入=DXではない
DXという言葉を聞いたとき、「ITツールの導入」や「業務のデジタル化」だけを指すと誤解しているケースは少なくありません。しかし本来のDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるIT活用にとどまらず、業務プロセスそのものやビジネスモデルを変革していくことを意味します。
そのため、「勤怠管理をクラウド化した」「ペーパーレスを進めた」といった取り組みはDXの“入口”ではあっても、それだけではDXとは言えません。情シスは「今ある課題を解決する手段」としてITを使うだけでなく、ITを通じて“業務のあり方そのもの”を見直すきっかけを作る役割を担っています。
現場と経営をつなぐ“翻訳者”としての情シス
中小企業においてDX推進を担う情シスには、「経営の意図」と「現場の実情」をつなぐ“翻訳者”のような役割が求められます。経営層が求める「効率化」や「競争力の強化」といった抽象的な目標を、現場の業務改善や仕組みづくりという具体的なアクションに落とし込むことが重要です。
そのためには、情シスが現場の課題やボトルネックを理解していることが前提となります。加えて、ITの言葉でしか語らないのではなく、「なぜこれが必要か」を現場の言葉で伝える力が問われます。
一方で、「情シスが全部やらなければならない」という思い込みは危険です。現場や他部署と連携しながら、小さな成功体験を積み重ねていくリーダーシップこそが、DX推進の鍵を握ります。
情シスが主導するDXの進め方【ステップ別に解説】
ステップ①:業務の現状把握とボトルネックの棚卸し
最初に取り組むべきは、「どこに課題があるのか」を現場目線で明らかにすることです。たとえば、書類のやり取りに時間がかかっている、誰が何の作業をしているか見えづらい、申請や承認が属人的で滞りがち…など、日々の業務の中にDXのきっかけは隠れています。
この段階では、現場ヒアリングや業務フローの洗い出しを行い、紙・Excel・メールなどで非効率になっている部分をリストアップしましょう。大がかりなシステム導入の前に、「変えやすいところから」「小さな困りごとから」着手するのが成功のコツです。
ステップ②:小さく始めて実績をつくる
現場での理解や協力を得るには、小さな改善でも「成果」を見せることが何よりの説得材料になります。たとえば、経費精算をクラウド化して月末の処理を30分短縮できた、共有ドライブを整備して資料探しの手間が減った、など「誰にとって、どんなメリットがあるのか」を数値や実感で示すことが重要です。
この段階で有効なのが、PoC(概念実証)として一部門だけでツールを試験導入する方法です。最初から全社展開を狙わず、「スモールスタート → 評価 → 横展開」のサイクルで徐々に広げていきましょう。
ステップ③:効果を数値化し、社内説得につなげる
改善の効果が出始めたら、それを“見える化”して社内に伝えることが次のステップです。DXは一部門で完結せず、部署をまたいで取り組む必要があるため、経営層・他部署への説明と合意形成が欠かせません。
「導入前後で作業時間が何%削減された」「エラー件数がこれだけ減った」といった定量的な成果を示すことで、「現場発のDXでも、ちゃんと結果が出せる」ことを証明できます。また、「次にどの業務に展開するか」のロードマップを描くことで、組織全体に波及するきっかけを作れます。
DX推進によくある課題とその解決策
現場が非協力的なときはどうする?
DXを推進しようとしてまずぶつかるのが、現場の“やる意味がわからない”という反発や無関心です。とくに中小企業では「今のやり方で十分うまくいっている」という声も多く、変化に対する抵抗が出やすい傾向にあります。
このようなときは、「現場の課題解決」にフォーカスした伝え方が有効です。たとえば「この入力作業、毎月何時間かかってますか? 自動化すれば1時間で終わります」といった具体的な改善メリットを示しましょう。ITではなく“現場の困りごとを解決する話”として届けることが鍵です。
また、改善を導入したチームの声を社内で紹介したり、ミニ勉強会を開いたりと、成果を“共有・可視化”することも協力を得やすくするポイントです。
予算が少ない・IT人材がいない場合の進め方
多くの中小企業では、DXに本格的な予算を割くのが難しいのが現実です。さらに、社内に専門的なIT人材がいないケースも少なくありません。
そこで有効なのが、「無料から使えるクラウドツール」「サポート付きで導入できるサービス」の活用です。たとえば、情報共有や案件管理などに対応した「クラウドサービス サスケ」のようなSFA・CRMツールは、使いながら仕組みを定着させやすく、専任人材がいなくても運用可能です。
また、作業の一部をサポートするAIアシスタント「カゲマル」のような軽量な支援ツールも、日常業務の効率化に役立ちます。「すべてを一気に変えようとしないこと」こそ、限られたリソースでDXを進めるための現実的なアプローチです。
よくある質問(FAQ)
DXって本当に必要?社内で疑問の声が出たときは?
「DXって結局、何がどう良くなるの?」という声に対しては、すでに改善された小さな成果を具体的に伝えることが有効です。「資料の提出が1日早くなった」「報告業務が週1回で済むようになった」など、目に見える変化を“数字”と“体験”で共有しましょう。
また、「人手不足」や「属人化」など、自社が直面している課題とDXのつながりを明示することで、“やらなければならない理由”が伝わりやすくなります。
自分が担当者でもプロジェクトを主導できる?
できます。ただし一人で抱え込むのではなく、関係部署との連携が前提です。
まずは「業務を改善したい」という声を拾い、小規模な改善提案から始めて実績をつくりましょう。その過程で、協力してくれる仲間を見つけていくことが大切です。
「現場の課題を拾って、ITで解決する」ことができれば、たとえ情シス専任でなくても、あなたがDXの“起点”になれます。
成功事例に学ぶ!現場発のDXで変わったこと
ペーパーレスと情報共有の徹底で業務効率アップ
ある中小企業では、毎月発生する報告書や日報の紙管理が大きな負担となっていました。特に、印刷・確認・保管・検索にかかる手間と時間がネックで、「必要な情報がすぐに見つからない」「ミスや二重管理が多い」といった課題を抱えていたのです。
そこでまず取り組んだのが、業務報告をクラウドで管理する仕組みの導入でした。紙の報告書をなくし、誰でもアクセスできるフォルダ構成に整理したことで、月10時間以上の工数削減を実現。さらに、リアルタイムでの情報共有や検索性の向上により、社内のコミュニケーションもスムーズになりました。
このように、一つの業務改善がチーム全体の“当たり前”を変えるきっかけとなり、「他の業務にも応用できそう」と社内の関心も高まりました。
クラウドサービス サスケを活用したナレッジ共有事例
営業部門を抱える別の中小企業では、属人化による“情報のブラックボックス化”が大きな課題でした。「あの顧客に何を話したかが分からない」「成功事例が引き継がれず埋もれてしまう」といった状態で、組織としての学びが蓄積されていなかったのです。
そこで導入されたのが、クラウドサービス サスケ。このツールでは、商談メモや活動履歴を簡単に入力・共有できるだけでなく、コメント機能やタグ付けによって“誰が、いつ、どんなやりとりをしたか”が一目で分かる仕組みが構築されました。
結果として、「成功した営業プロセスの再現」「新人育成への活用」「案件の引き継ぎ効率の向上」など、組織全体で“知見を活かす”文化が根付きはじめたのです。
こうしたツールの活用によって、“情報が見える化されたこと”そのものがDXの成功体験となり、他部門にも導入を広げるきっかけとなりました。
中小企業のDX推進におすすめの支援ツール
タスクの属人化を防ぎ、情報を“見える化”するには?
DX推進の大きな目的のひとつが、「情報の透明性」と「チームでの共有体制の確立」です。属人化した業務や、口頭・メールベースのあいまいな引き継ぎは、業務の非効率とトラブルの温床になります。
その解決策として有効なのが、日々のタスクや情報を“記録・共有・蓄積”できる仕組みの導入です。業務フローを可視化し、誰でもアクセスできる環境をつくることで、「あの人に聞かないと分からない」状態を減らすことができます。
Excelや紙に依存しがちな中小企業でも、クラウドベースの情報共有ツールを導入することで、DXの基盤となる“共通言語”が整い始めます。
サスケの活用でできること
クラウドサービス サスケは、営業支援(SFA)・顧客管理(CRM)を中心に、情報の一元管理と社内共有を実現するプラットフォームです。具体的には、以下のような活用が可能です。
- 顧客対応履歴や提案内容を記録し、ナレッジとして蓄積できる
- タグやコメント機能で、チーム全体の情報把握がスムーズに
- 案件の進捗や商談履歴を見える化し、会議や引き継ぎも効率化
こうした仕組みによって、特定の担当者に依存しない体制づくりが進み、結果として“組織的に営業・対応できる仕組み”が構築されていきます。
また、導入にあたっても専門的なITスキルは不要で、“日々の業務で自然に使えるUI・設計”になっているため、DXの入り口として非常にハードルが低いのも特長です。
簡易的なチャットAI導入ならカゲマルも選択肢に
定型作業や確認作業にかかる時間を短縮したい場合は、AIアシスタント「カゲマル」の活用もおすすめです。カゲマルは、社内のマニュアルや資料と連携して、問い合わせ対応・文書検索・簡易的な議事録要約などをAIが自動で支援します。
たとえば、「この申請書ってどこにある?」「〇〇の手順を教えて」といったよくある社内問い合わせを、AIが即座に返答。これにより、人が何度も対応する時間を削減し、“本来やるべき業務”に集中できる環境が整います。
コストや導入負担も抑えられるため、情シスやDX初心者でも手軽に“効率化体験”をスタートできる選択肢として注目されています。
まとめ:情シスが「できる範囲から始める」DXが成功のカギ
「DX=全社変革」など大きな構えで始めると、現場の負荷や抵抗が先に立ち後戻りしてしまいがちです。
それよりも、小さな業務改革から実験を重ね、徐々に広げていく姿勢こそが、中小企業のDX成功に不可欠です。
情シスは中立の“橋渡し役”として、現場の声を取り込みながら、“無理しない範囲で変えること”を積み重ねることから始めましょう。
DXを“現場で使われて成果を生む基盤”に変えたいなら、サスケ
DXを始める際、ツールだけを入れても“使われない投資”に終わることは珍しくありません。
クラウドサービス サスケ は、業務の可視化・定着設計・現場適応を重視した設計で、DXを“現場で使われる仕組み”に昇華させるツールです。
- 顧客・リード・商談情報を 一元管理 し、情報の分断をなくす
- AI による優先提案・スコアリングで、現場判断の精度とスピードを支援
- メール配信・ナーチャリング・タスク管理を統合し、業務の流れをシームレスに
- スモールスタート導入 に対応し、段階的な展開でリスクを低減
- 操作性を意識した UI/UX 設計で、ITに不慣れな現場でも使いやすい
- 活動ログ・KPI可視化のダッシュボードで、変化を「見える成果」として共有
DXを“現場に根づく変化”にしたいなら、まずはサスケを選択肢に加えてみてください。
無料デモ・資料請求で、実際の使い心地と成果を体感してみてください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
最新の投稿
 営業2025年10月16日【2025年版】AI自動化とは?導入メリット・失敗しない進め方・中小企業事例とおすすめツール
営業2025年10月16日【2025年版】AI自動化とは?導入メリット・失敗しない進め方・中小企業事例とおすすめツール 営業2025年10月15日CRM運用を成功させる設計と定着ノウハウ|サスケ/カゲマル活用も含めた実践ガイド
営業2025年10月15日CRM運用を成功させる設計と定着ノウハウ|サスケ/カゲマル活用も含めた実践ガイド 営業2025年10月15日【2025年版】CRMの主な機能とは?営業効率化に役立つ機能一覧と選び方
営業2025年10月15日【2025年版】CRMの主な機能とは?営業効率化に役立つ機能一覧と選び方 サスケの使い方2025年10月15日【活用術】リード管理で成果を上げるサスケのおすすめ機能5選
サスケの使い方2025年10月15日【活用術】リード管理で成果を上げるサスケのおすすめ機能5選