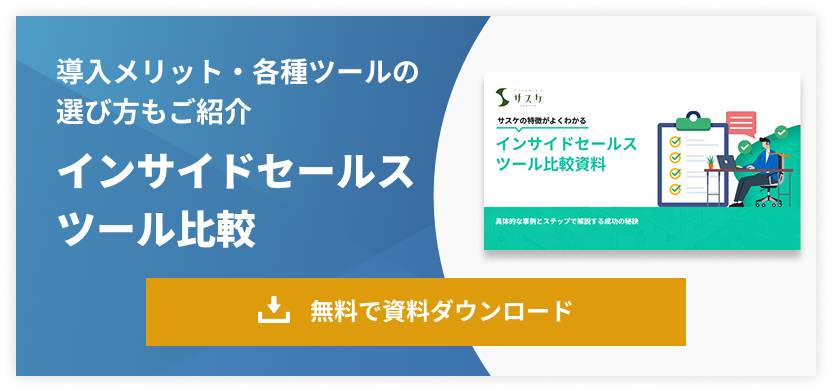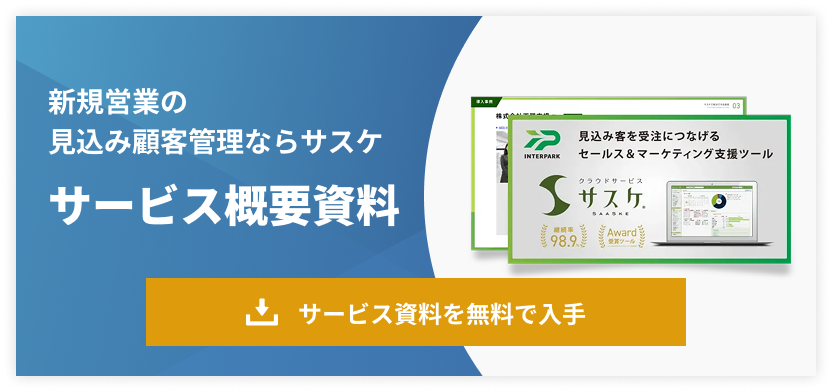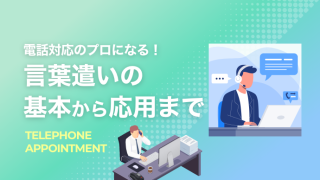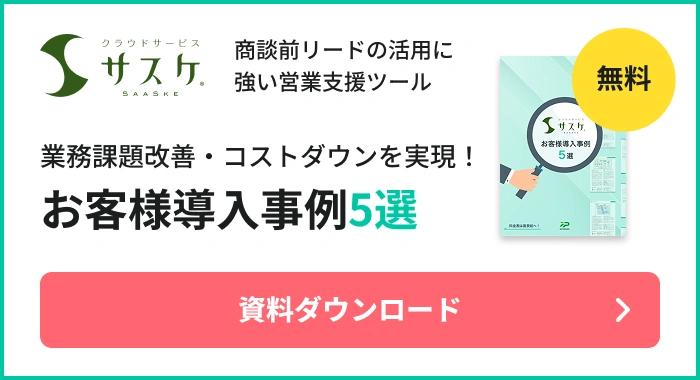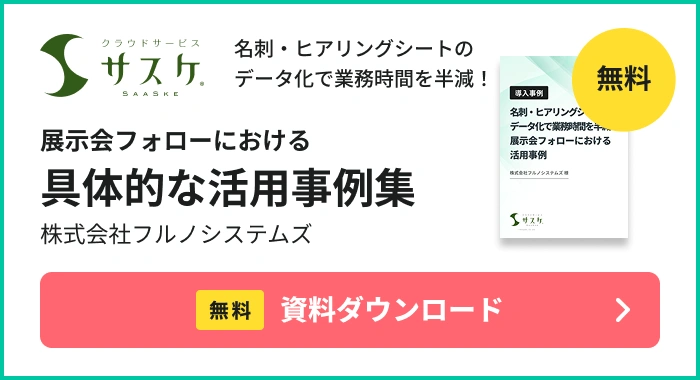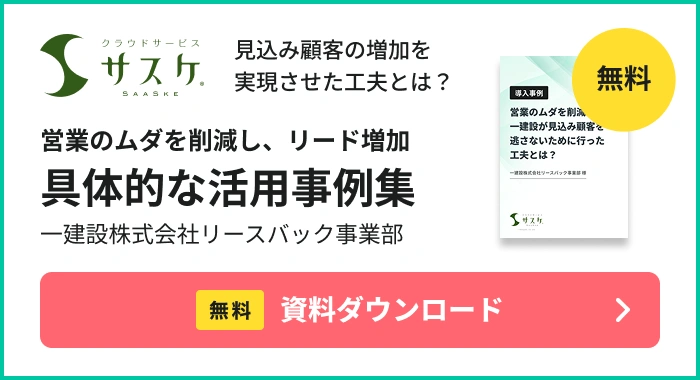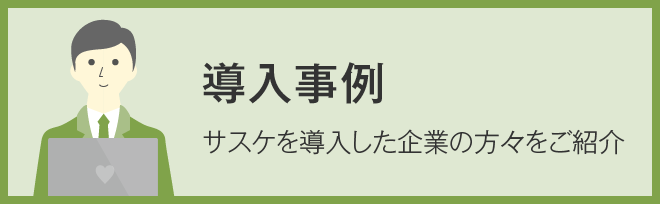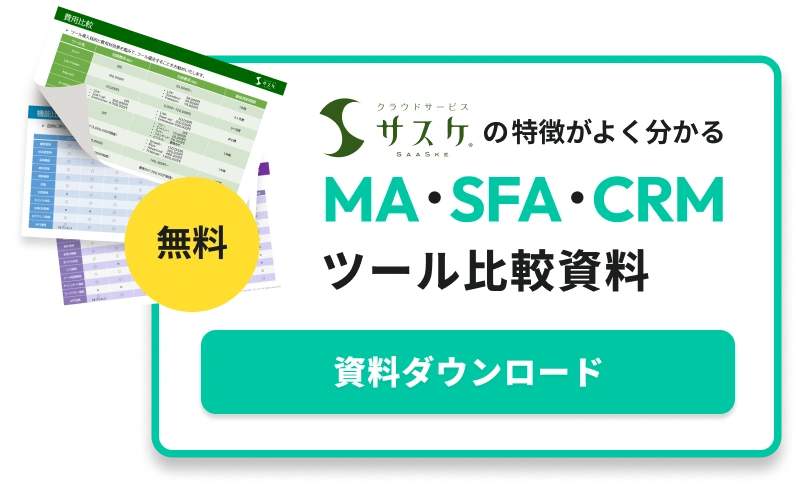訪問営業中心の時代から、オンライン・電話・デジタル接点を活用する営業体制へ——。今、多くの企業で「インサイドセールスの立ち上げ」が急務となっています。
しかし現場では、「何から始めればいいのか」「成果につながる体制をどう作るのか」が分からず、立ち上げが停滞しているケースも少なくありません。
本記事では、ゼロからインサイドセールスを構築するための具体的ステップを、実際の現場目線で解説します。目的設定・体制構築・ツール導入・KPI設計までを体系的に整理し、失敗しない立ち上げの型を掴める内容です。
Contents
なぜ今、インサイドセールス立ち上げが求められているのか
営業効率化と顧客接点の多様化
近年、リードの獲得経路が多様化し、営業担当者がすべての顧客対応を行うのは非現実的になりました。展示会・ウェビナー・Web問い合わせなど、見込み顧客との初期接点を効率的に商談へつなげる役割として、インサイドセールスが注目を集めています。
さらに、リモート営業やハイブリッドワークの定着により、オンライン中心の営業モデルを整備する必要性が高まっています。属人的な営業活動を脱し、「再現性のある仕組み化」を実現することが、組織の成長に直結する時代です。
立ち上げでまず整理すべき「目的」と「ゴール」
インサイドセールス立ち上げで最初にすべきは、「何のために導入するのか」を明確にすることです。
- 新規商談を増やしたいのか
- 営業担当の負荷を減らしたいのか
- 休眠リードを再活性化したいのか
目的によって体制設計やKPIの方向性が大きく変わります。
「目的不在の立ち上げ」は、形だけの体制になり失敗の原因となります。まずは経営層・営業・マーケティングの認識を揃え、“成果指標の定義”から始めましょう。
立ち上げ前に押さえるべき3つの準備
現状分析:営業課題・リード管理・商談化率の把握
成功する企業ほど、立ち上げ前に「現状を定量的に把握」しています。
- どのリードソースが多く、どの段階で失注しているか
- 商談化率や接触率はどれくらいか
- リード管理が個人やExcelに依存していないか
これらを可視化することで、「どの部分をインサイドセールスで補うべきか」が見えてきます。
現状分析は立ち上げの出発点です。数値と事実で課題を洗い出すことが、正しい戦略設計につながります。
役割分担とチーム体制の設計
インサイドセールスの立ち上げでは、「誰が・どこまで・どの指標を追うか」を明確にすることが重要です。
営業(FS)とマーケティングの中間で動くインサイドセールスが、情報共有のハブとなります。
- リード創出:マーケティング
- 商談化:インサイドセールス
- 受注:フィールドセールス
この流れを整理し、「役割の境界線」と「連携の仕組み」を設計することで、部門間の摩擦を減らし成果が安定します。
社内合意の取り方と情報共有の仕組み
多くの企業がつまずくのが、社内理解の欠如です。
「営業の仕事を奪うのでは?」という誤解や、「立ち上げ目的が共有されていない」ことで、現場の協力を得られないケースがあります。
この段階では、
- インサイドセールス導入の目的と期待成果を明文化
- 定例会やチャットツールで情報共有ルールを明確化評価制度への反映(商談化数・貢
- 献度など)
といった、組織的な合意形成の仕組みが欠かせません。
ステップ①:目的を明確にしKPIを設定する
商談化率・接触率・受注率の基礎指標
インサイドセールスのKPIは、「活動量」と「成果指標」に分けて設計します。
- 活動量KPI:架電数、接触件数、メール開封率など
- 成果KPI:商談化率、受注率、リード転換率など
初期段階では“活動量のKPI”を重視し、徐々に成果指標へ移行するのが理想です。数値の積み上げがチームの成長を見える化し、改善サイクルを作りやすくします。
成果を出す組織に共通するKPI設計の考え方
成果を出す組織に共通しているのは、「KPIが目的と連動している」ことです。
例:
- 新規商談数を増やしたい → 商談化率、接触率を重視
- リード育成を目的とする → メール開封率、ナーチャリング率を重視
また、KPIの設定は“個人評価”よりも“チーム成果”に紐づけることがポイント。数値目標を共有し、全員で改善サイクルを回せる文化を作ることが、立ち上げ成功の第一歩です。
ステップ②:人員体制と運用ルールを整える
ロール設計(IS/FS/マーケ)の基本
インサイドセールスの立ち上げでは、「誰がどこまでの役割を担うか」を明確にすることが最優先です。
典型的な構成は以下の通りです。
- マーケティング(Marketer):リード獲得・スコアリング・ナーチャリングを担当
- インサイドセールス(IS):架電・メール・ヒアリングを通じた商談創出
- フィールドセールス(FS):商談・提案・クロージングを担当
この3者がそれぞれの役割を明確に理解し、“顧客情報を連携する流れ”を構築することで、リードが途切れずに受注まで進みます。
トークスクリプトとナレッジ共有で属人化を防ぐ
立ち上げ初期は、担当者ごとのスキル差が成果に直結しがちです。
そのため、トークスクリプト・メールテンプレート・FAQ集などの“ナレッジ共有”が必須です。
具体的には、
- 初回架電時のトーク例(興味喚起型/課題ヒアリング型)
- 反応別の対応パターン(温度感別スクリプト)
- 商談化できなかった理由の分析・共有
を定期的に整理し、属人化を防ぎながら改善サイクルを作ることが重要です。
特に新任担当者の教育にも役立つため、「仕組みで再現できる営業力」が組織に定着します。
ステップ③:ツール導入で仕組み化を進める
導入すべきツールの種類と選定ポイント(SFA/CRM/MA)
インサイドセールスを効率的に運用するには、データを一元管理するツール導入が欠かせません。
代表的なツールは以下の3つです。
- SFA(営業支援):商談・活動履歴・案件進捗を可視化
- CRM(顧客管理):リード・顧客情報を統合してフォロー漏れを防止
- MA(マーケティング自動化):メール・スコアリングなどリード育成を自動化
選定のポイントは、「現場が使いこなせるか」「既存業務と連携できるか」です。
ツールの機能よりも、運用のしやすさ・社内浸透性を重視することが、長期的な成功を左右します。
リード管理を効率化する「クラウドサービス サスケ」の活用
インサイドセールスの成果を安定化させるには、リード管理の仕組み化が必要です。
「クラウドサービス サスケ」は、リード管理×AIを活用した営業支援システムで、立ち上げ初期に最適なツールです。
AIによる優先リード抽出とデータ統合
サスケでは、過去の活動履歴や反応データをもとに、商談化の可能性が高いリードをAIが自動抽出。
これにより、担当者が“架電すべき相手”を効率的に判断でき、成果につながるアプローチが実現します。
また、展示会・Webフォーム・名刺など複数の流入経路を一元管理できるため、リードの重複・漏れを防止します。
属人化を防ぐ運用の仕組みと実例
サスケは、架電・メール・商談履歴をすべて時系列で蓄積できるため、引き継ぎやKPI管理がスムーズです。
実際、インサイドセールス立ち上げ期の企業で、
- リード情報を一元化
- 商談化率を20%以上改善
- 担当者ごとの成果差を縮小
といった成果が出ています。
属人化を防ぎながら、「チーム全体で成果を再現する仕組み」を実装できるのがサスケの強みです。
ステップ④:改善サイクルを回し続ける
週次・月次で見るべき指標と改善の進め方
立ち上げた後こそ、データに基づいた改善が鍵となります。
週次では「架電数・接触率・商談化率」、月次では「受注率・ROI・リードの質」を確認し、仮説→検証→改善のサイクルを習慣化させましょう。
ツールで可視化されたデータをもとに、“行動ではなく成果を議論する文化”を育てることが、持続的成長につながります。
KPIレビューで成果を継続的に高める
KPIは一度決めて終わりではなく、状況に応じて見直す柔軟性が必要です。
例えば、商談化率が想定より低い場合はトークスクリプトを改善し、接触率が低い場合はアプローチチャネルを見直すなど、定期的なレビューで“改善が前提の組織”をつくりましょう。
失敗しやすい企業の特徴と成功のポイント
目的が曖昧なまま人を配置してしまう
「まずはやってみよう」でスタートすると、KPIも評価基準も曖昧になり、成果が見えません。
立ち上げ前に必ず「なぜインサイドセールスを導入するのか」を定義し、ゴールと成果指標を明確にしましょう。
ツール導入が目的化している
ツールを導入しただけでは何も変わりません。
大切なのは、データをもとに“どう改善するか”を考える運用体制をつくることです。
ツールは手段であり、目的は「再現性のある商談創出」。
営業部門と連携できず成果が分断される
インサイドセールス単体では成果は出ません。
FS(フィールドセールス)との連携を仕組み化し、商談移行後のフィードバックを得ることで、リードの質を高めていくことができます。
成功企業の共通点:小さく始めて継続的に改善する
最初から完璧を目指さず、2〜3名体制のスモールスタートから始めて検証→改善を繰り返す企業が成功しています。
立ち上げは“構築”ではなく“運用で育てる”もの。スピード感を持って改善できる体制を意識しましょう。
よくある質問(FAQ)
立ち上げにどれくらいの期間がかかる?
平均的には3〜6か月程度です。初期はテスト運用を兼ねて体制を固め、半年以内にKPIを定量化するのが理想です。
専任人員を確保できない場合の進め方は?
まずは営業メンバーの一部を兼任で配置し、成果が見えてから専任化するのがおすすめです。
ツールを活用すれば、少人数でも十分に運用可能です。
ツール導入はどの段階で行うべき?
「目的・KPI」が固まった後がベストタイミングです。
最初からツールに依存するのではなく、課題を明確化してから導入→定着化を図ることで、失敗を防げます。
まとめ:インサイドセールス立ち上げは「仕組み」と「継続」が鍵
まずは目的を明確にし、小さく始める
立ち上げの成否は、最初の「目的設定」にあります。
曖昧なまま進めず、“どんな成果を出したいのか”を明確にしてから動くことが成功の第一歩です。
改善を文化にできる組織が成果を出す
インサイドセールスは、一度仕組みを作って終わりではありません。
データに基づき、改善を習慣化できる組織こそが長期的な成果を出します。
そのためには、見える化と仕組み化を支えるツールの活用が欠かせません。
インサイドセールスの立ち上げなら、サスケ
クラウドサービス「サスケ」は、リード管理×AIで新規営業を仕組み化できるSFA/CRMツールです。
案件化前のリードを一元管理し、AIが商談化確度をスコアリング。
担当者の勘や経験に頼らず、“成果が出るアプローチ”をチーム全体で再現できます。
さらに、架電・メール・商談履歴を可視化することで、インサイドセールス立ち上げ期の課題——属人化・漏れ・非効率——を根本から解消。
少人数でも高い成果を出せる営業組織を目指すなら、今すぐ「クラウドサービス サスケ」をチェックしてみてください。
投稿者

- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。